資料ダウンロード
rayoutはファンマーケティングを活用した
PRをご支援しています
閉じる
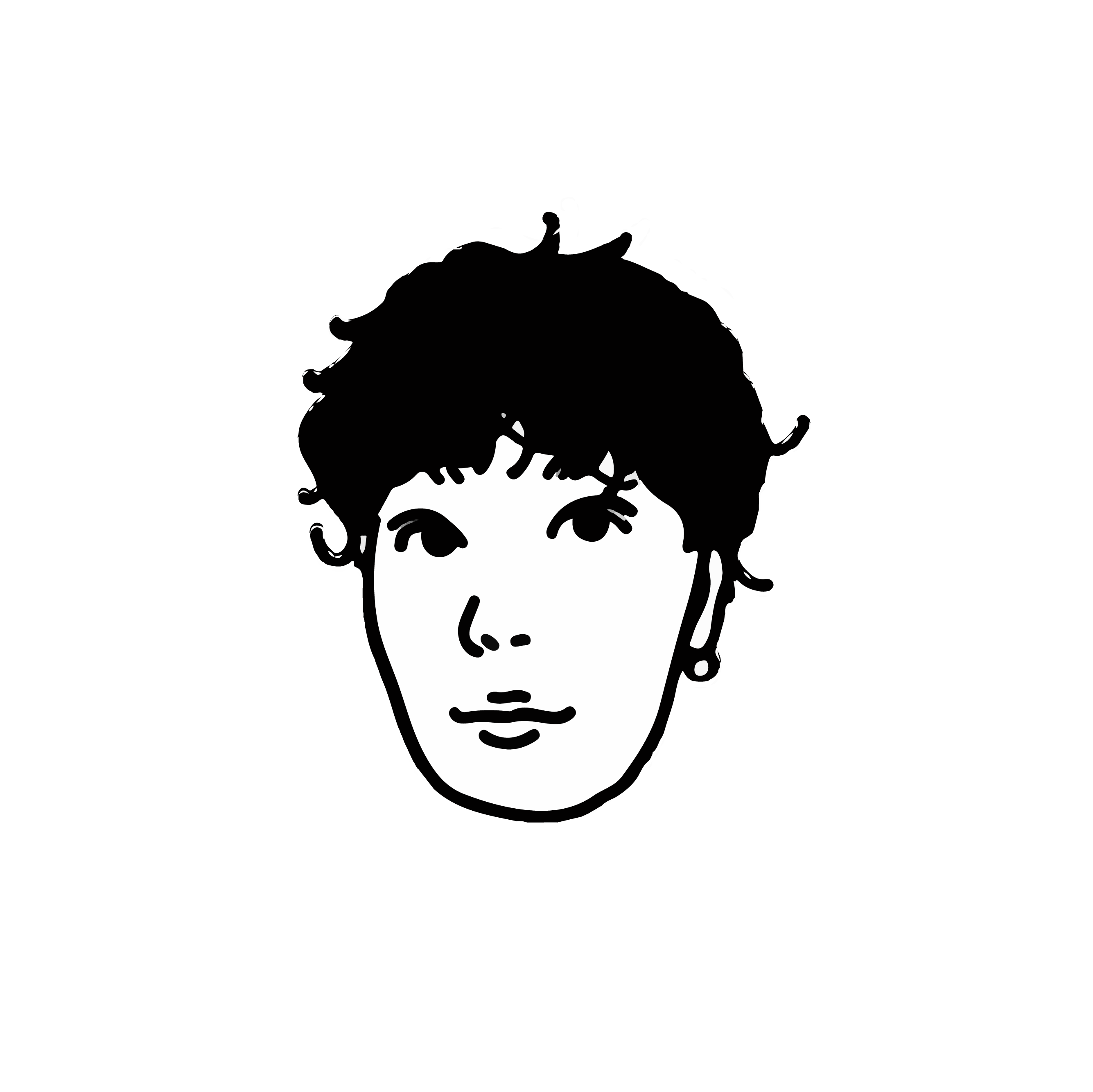
Shibashi

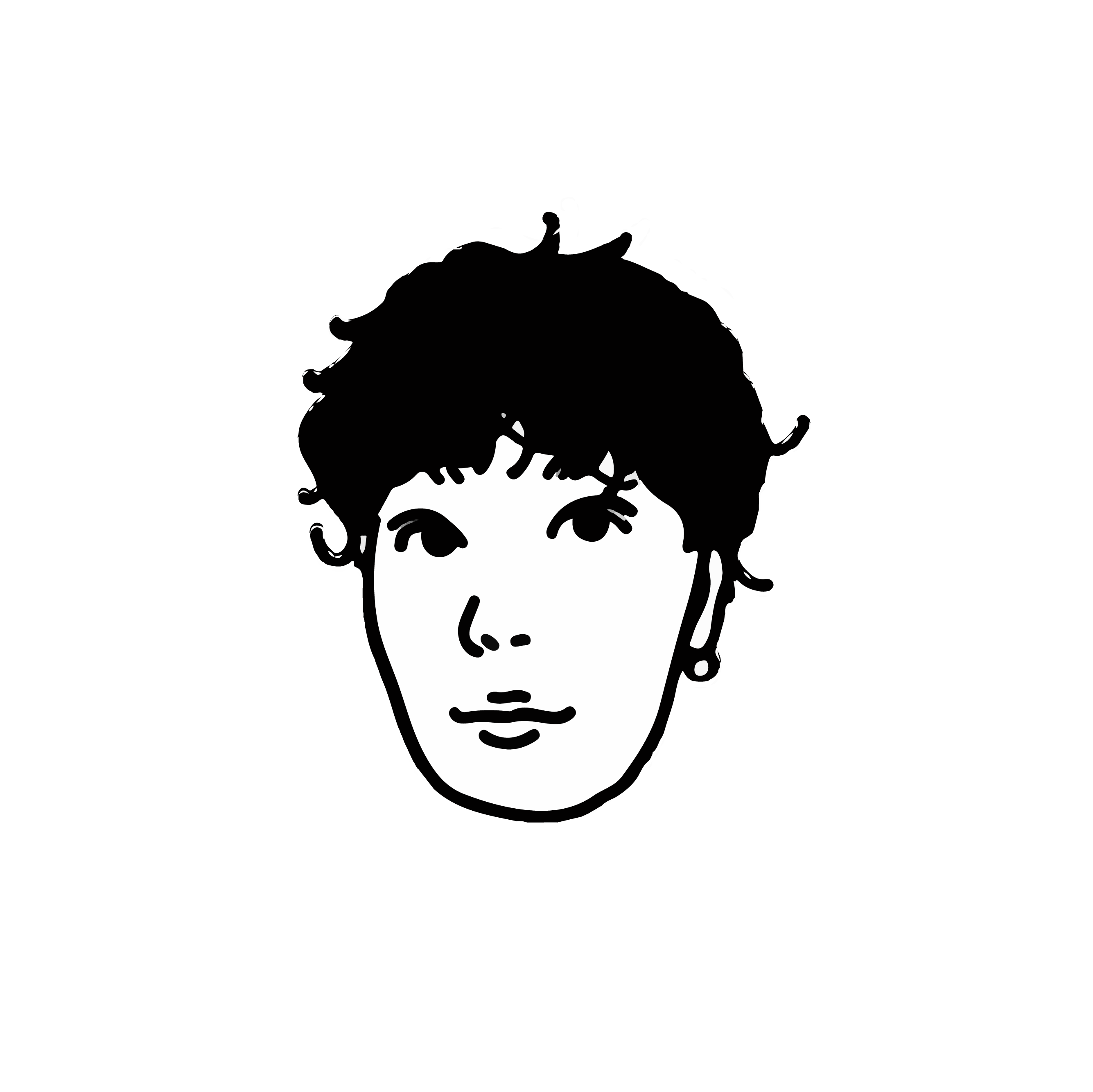
Shibashi
こんにちは、&Fans編集部の椎橋です。&Fans では、熱狂を生むさまざまな企業や個人のストーリーや、それらの考えに紐づくマーケティング概念などを紹介しています。
今回は、保育総合ICTサービス「ルクミー」で社会課題解決を目指すリーディングカンパニー、ユニファ株式会社の高浦さんにお話を伺いました。
家族とのより豊かな時間を創出するため、そして社会の課題に対し自らが先頭に立って解決を導くという強い信念と使命感を抱き、保育AI™を中心とした最新のテクノロジーを駆使して課題解決に挑むユニファ株式会社。
「家族の幸せを生み出す あたらしい社会インフラを 世界中で創り出す」というパーパスのもと生み出されたサービス「ルクミー」に込められた情熱、保育という領域で多くの保育者や保護者から支持を集めている理由について伺いました。
目次
「ルクミー」は、保育者の業務負担を軽減し、こどもとより深く向き合える豊かな環境を整えるための、保育施設向け総合ICTサービスです。保育園、幼稚園、こども園などで、保育者が抱える様々な課題解決や理想の実現をサポートする幅広いサービスを展開しています。
サービス内容は大きく「ICT」「ヘルスケア」「フォト」の3つに分けられます。
「ICT」サービスでは、これまで手書きで行っていた連絡帳や指導計画、日誌といった帳票管理などをアプリで一括管理できるようになります。従来、指導計画や日誌などは紙に手書きで作成することが多く、職員間の確認や承認、書類作成に時間を奪われるケースが多くありました 。これらの業務を効率化し、電子化することで、シームレスに作業を進めることが可能になります。また、これまで紙に印刷して管理していた資料もアプリでの管理になることで、紙資源の削減にも貢献します。
そうなんです。ただ、多くの園でいまだに手書き文化は残っており、「ルクミー」は、アプリをダウンロードした端末から誰でも操作できるため、保護者の方にも、忙しい朝に連絡帳などを手書きする手間がかからず、通勤途中で気軽に入力するといった使い方もしていただいています。
また、「ルクミー」では、こどもがいつ登園し、いつ降園したかといった登降園の時間管理も可能です。これにより保育料の計算も自動化でき、それまでエクセルで管理・計算していた業務が効率化されます。
このように、保育園や幼稚園の先生、保護者、そして経営者といった、保育に関わる全ての人に負担軽減をもたらすことができるシステムを構築しています。
今まで時間を割いていたアナログな作業を削減することによって、こどもたちと直接触れあう時間が増え、保育の「質」も向上していきます。
ヘルスケアサービスである「ルクミー午睡チェック」は、こどもの午睡(お昼寝)を見守り、保育者の精神的負荷をサポートするサービスです。主に乳児向けに開発され、午睡中の見守りを強化することを目指しています。体の動きを検知する体動センサーを腹部に装着することで、うつ伏せ寝をした際にアプリによってアラートが出る仕組みになっています。
従来は、事故防止や監査のため、保育者が5分おきにこどもの向きを手書きで記録する必要がありました。緊張感の高い作業を、細かい間隔で何度も行うことは大きな負担となっていたのです。しかし、「ルクミー午睡チェック」はアプリと連動しており、こどもの体動をセンサーが検知し、アプリが全て自動で記録します。さらに、こどもがうつ伏せ寝状態が一定秒数経過するとアラート音が鳴る機能も備わっています。
目視でのチェックは引き続き並行して行われますが、「ルクミー午睡チェック」を活用することで、こどもの安全確保がさらに向上し、手書きでの記録による保育者の負担軽減にもつながります。
「フォト」は、園で撮った写真を「ルクミーフォト」を通じて保護者が閲覧・購入することができます。園でしか見られないこどもの表情や、友達、先生との関係性を見ることができ、写真をきっかけに家族間で会話が生まれ、こどもの成長を促すことにもつながります。
「ルクミーフォト」のアプリにアップロードすると、クラスや日付分けが自動で行われます。写真の整理や確認に対する業務負担もカバーするシステムになっています。
事前にこどもたちの顔認証を登録していれば、写っているこどもたちの写真の量のばらつきも確認できるので、どのご家庭にも公平に写真を共有することができます。
「ルクミーフォト」を導入する前には、一部の保護者からのお叱り等を恐れて写真を載せなくなってしまう、というケースを抱えている園もありましたが、それは保護者全体の満足度低下に繋がる可能性もあります。「ルクミーフォト」では、AI機能を活かし、写真のばらつきがないよう対応ができるため従来よりも安心して写真を共有することができます。
私たちが一番重視しているのは「こどもの成長」です。
こども家庭庁も「こどもまんなか社会」という形で、こどもたちの権利が保障された健やかな成長を社会が推し出し、幸せに生活することを掲げていますが、私たちのサービスも同様のコンセプトを持っています。
「ルクミー午睡チェック」のように、こどものお昼寝の見守りを強化することはもちろん、「ルクミーフォト」を利用してこどもの成長を切り取って見守り、その写真が家族の幸せのきっかけ作りになることなどを願って日々邁進しています。
業務の改善や負担軽減によって、保育者にはゆとりのある時間が生まれます。これは、保育者がこどもと直接向き合い、触れ合うことに専念できる時間が増えることを意味します。保育者の多くは、こどもの成長をしっかりと見守り、深く関わりたいと考えている人たちの集まりです。保育者の本質的な部分を叶えることが、安定した働き方や、安全性の高い保育への成長につながると考えています。
業務に忙殺され、事務負担も強く、こどもと向き合いたいと思ってもそれが叶わない、という声が多く上がっていました。私たちは、そういった課題を踏まえ、保育者の望む環境をサポートすることにも力を入れています。
現在、保護者のニーズは多岐にわたっていると感じています。こどもの探求心を促し、興味のあることを見つけ出してほしいと願うご家庭は非常に多く、保育の中でこどもたちの内面の教育について学びを得たいと思っている方が増えています。私たちは、そういった「こどもたちが抱いている興味」の部分を抽出しデータ化するサービスに着目しています。
例えば、「ルクミーフォト」にアップロードされた沢山の写真には、どのようなものに対して笑顔を向けているか、何に興味を示した表情をしているか、一緒に写っているこどもたちの関係性はどのような構成かなど、多くの情報が蓄積されています。これらの情報は、たとえば今後の学習のパーソナライズ化や、その子に合った探求の支援に役立つほか、保育の「質」そのものを高めていくための基盤データとしても活用されていくと考えています。
保育者側においては、連絡帳のテキストデータや画像データをAIに読み込ませることで、こどもの成長の様子を前後の文脈もふまえた“ストーリー”として整理することができます。単なる断片的な記録ではなく、「この子は最近こんな変化があった」「こんなことに興味を示している」といった一貫した視点が浮かび上がるのです。
これにより、レポート作成の負担を軽減し、より深い気づきや思いのこもった内容に時間をかけられるようになります。これらの取り組みは、こどもの成長に対するアプローチをより一層深め、保育の「質」の向上に繋がると考えています。
「連絡帳や日誌を作成する際にどのように書けばいいか悩む」といった相談を受けることがあります。こういった問題も「ルクミー保育AI」を使えば、テキストの大規模言語処理の機能を用いることで、予測や参考例などを基に、簡単に文章作成をすることができるようになります。
AIの有用性は皆さんも認識し始めているので、この技術をしっかり打ち出していくことは、次のステージへの推進力として非常に重要な要素であると考えています。
保育業界全体の環境を良くすることが、我々の社会課題解決に対する役割であり、使命だと考えています。私たちは「ルクミー」を取り入れたことによって、その保育園や幼稚園、こども園等が「すごく先端的な園」として見られることを望んでいるわけではありません。あくまで、保育AIを中心としたテクノロジーを使うことによって、保育の[質]が上がる貢献ができているかを重要視しています。
現場で働く保育者の皆さんは、「保育の質を上げたい」と心から思っています。費用や導入コストなど、乗り越えなければならないものもありますが、それを乗り越えて導入した結果、業務が著しく改善し、こどもたちとの触れ合いが高まっています。
このような事例をしっかりと伝え、「ルクミー」によって、それぞれの園が望むスタイルになるために、どうすればよいのか導いていくことが必要だと考えています。
単純に「ルクミー」を活用していただくだけで終わりではなく、「ルクミー」をきっかけに保育業界全体が、幸せに満ちた社会へ一歩ずつ進んでいくようなイメージで、世界をリードできる存在でありたいと思っています。
本当にそう思います。だからこそ私たちは、こどもたち一人ひとりの成長や興味をより深く理解し、未来につなげていく取り組みも進めています。その1つが、写真や日誌などのデータからこどもたちの興味や思考を抽出していく「こどもデータ」です。この「こどもデータ」は、退園して小学生になった後も、「生涯データ」として活用できる可能性があります。
幼少の頃の体験や気持ちは、その後の人生を左右する大きなものです。このような幼少期の体験を大切にすることが世の中で広まりつつあることを感じているため、それに対しどのようなサービスを提供していくか、慎重に進めています。可能であれば、ユニファがその先端に立ち、リードできる存在でありたいと思っています!
人材確保や賃上げといった目先の課題に注視するのではなく、保育者の胸の奥にある「こどもたちと触れあって保育の質を上げたい」という気持ちを大切にする。そんなシステムを開発、提供をしているユニファ株式会社に、人肌に触れた時のような温もりを感じました。
「ルクミー保育AI」機能の可能性には、思わず舌を巻いてしまいましたが、最先端テクノロジーを瞬時に取り入れるスピードがあるからこそ、社会課題に対して柔軟にアプローチが出来るのだと感じました。
家族との時間を大切にする。こんなに当たり前なことが叶わなかった時代が終わる。そんな希望の光が胸に灯りました。
愛とテクノロジーを掛け合わせたユニファ株式会社のこれからの活動に、ますます目が離せなくなりました。
取材・執筆:椎橋萌美
編集:神谷周作

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi