資料ダウンロード
rayoutはファンマーケティングを活用した
PRをご支援しています
閉じる
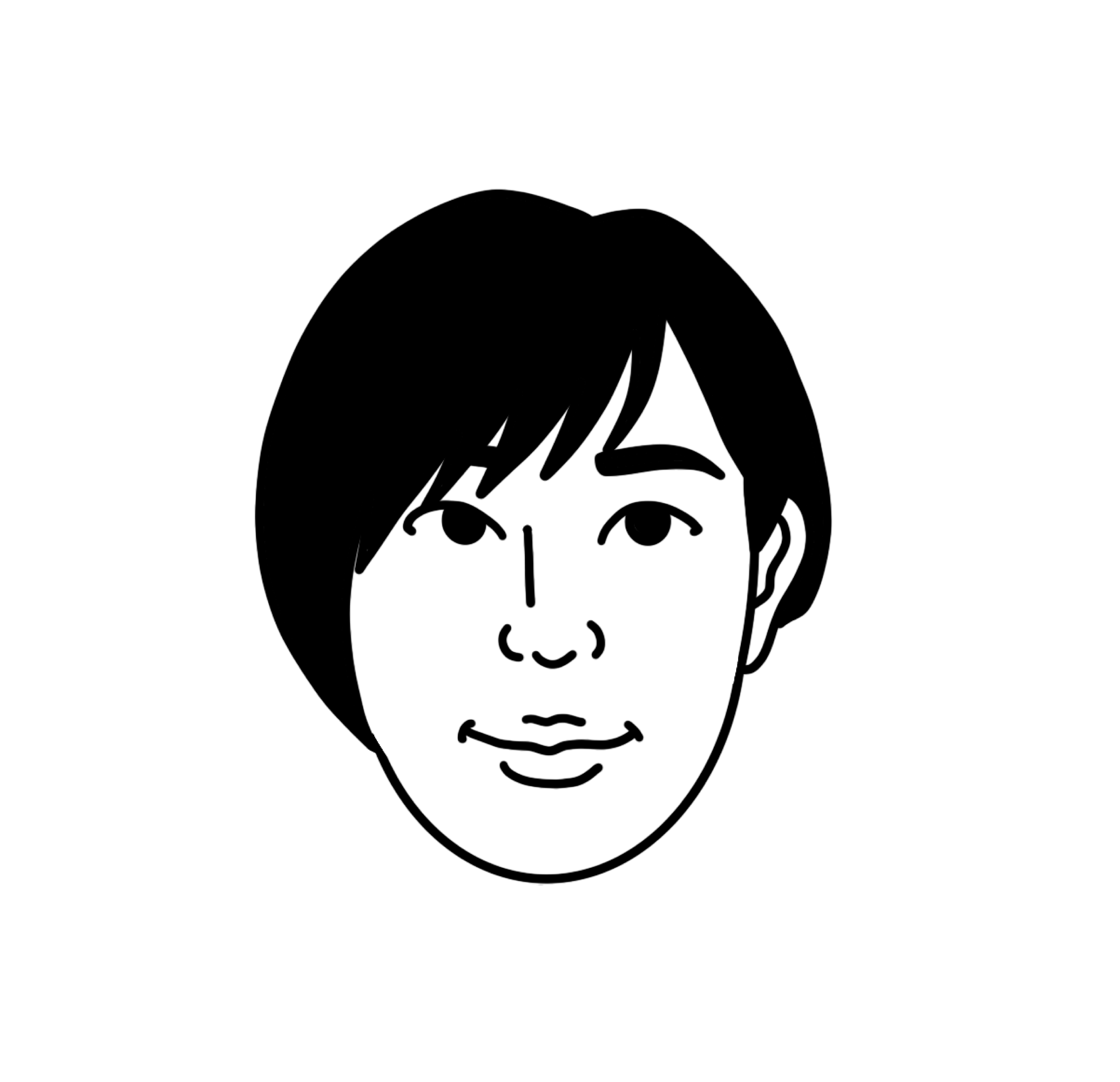
Matsui

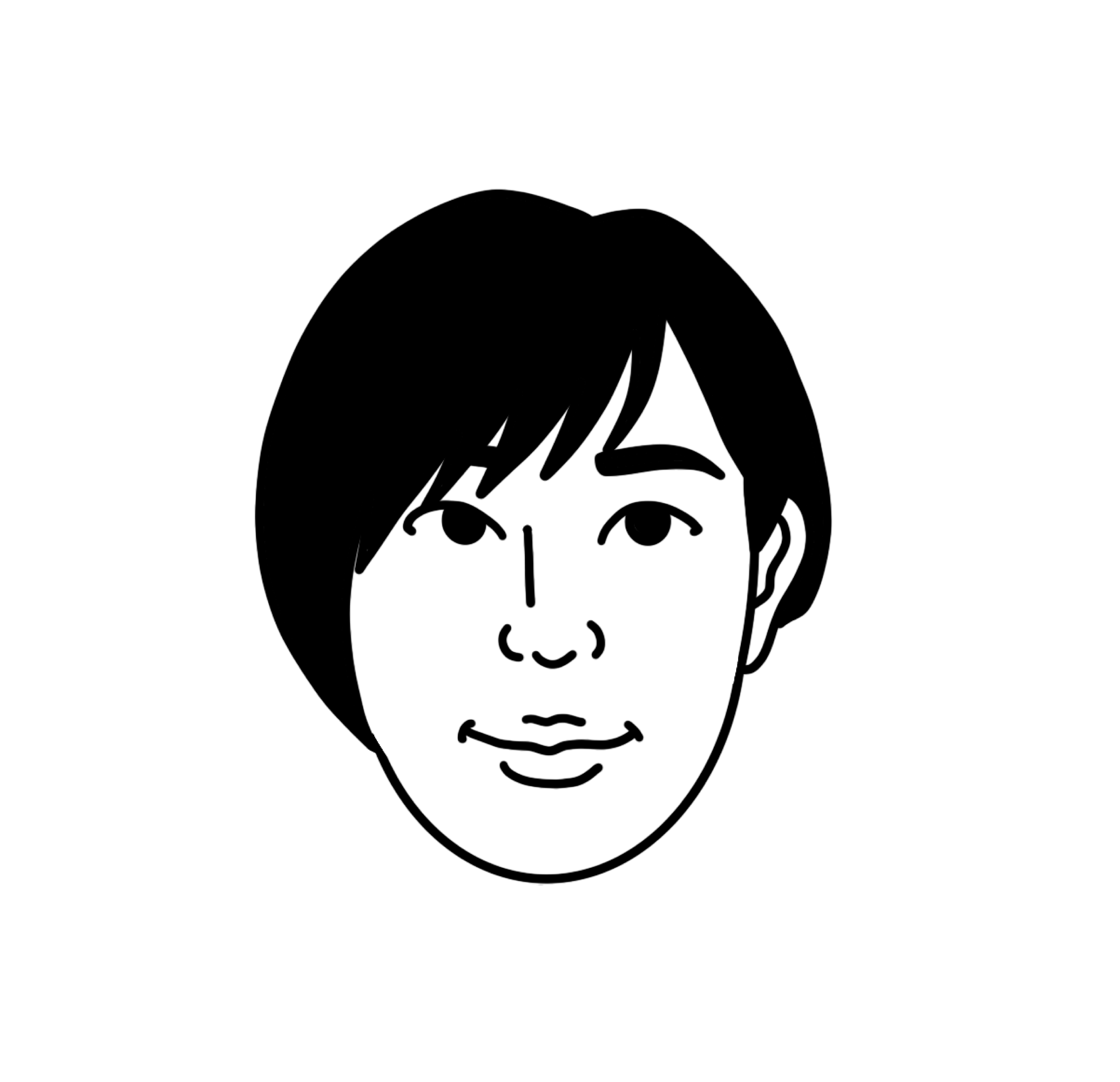
Matsui
こんにちは、&Fansライターのマツイです。
&Fansでは、熱狂を生む企業や個人のストーリー、それらの考えに紐づくマーケティング概念などを紹介しています。
世界有数の大都市である東京。多くの企業や人が集まり、都心には超高層ビルがひしめいています。しかしそんな大都会のイメージとは裏腹に、都内には豊かな自然が残るエリアもあるのです。
それは「奥多摩」。
島しょ部を除く東京都内唯一の村を擁するこのエリアは、都心とは違った魅力にあふれる場所。
社会活動と地球環境の共存に取り組む「Social Plastik(ソーシャルプラスチック)」は、このエリアを中心に活動を展開しています。
そこで今回は、Social Plastikの活動や輪を広げる取り組みについて、代表の大釜翼さんにお話を伺いました。
目次
リバースプロジェクトは、「人類が地球に生き残るために」という問いのもと、未来におけるサステナブルな生活のあり方を追求する取り組みです。2008年から、プロジェクトや事業を通じて、クリエイティブな視点から社会課題の解決に取り組んでいます。
具体的には、企業や行政などとパートナーシップを結び、衣食住・教育・まちづくり・アートなど、幅広い領域における最適解を見出し、町おこしやコミュニティづくりを提案しています。
リスタートを切ったのは2020年、ちょうどコロナ禍でした。
世の中が不安で落ち着かない状況でしたし、その前後には大きな災害も起こっていました。そんな中で「会社として何をするべきか」と考えたときに、改めて社会課題を解決するプロジェクトしかないと思ったんです。それを社会に実装し、各地域でうまく循環する仕組みを作ろうと生まれたのが「リバースプロジェクトヴィレッジ構想」です。
はい。現在は、奥多摩を中心にさまざまな取り組みを行っています。有志で始まったプロジェクトですが、ありがたいことに認知度は少しずつ上がってきていて嬉しい限りです。
プロジェクトを展開していくうえで、その地域である意味が必要だと思っていたんです。
僕は生まれも育ちも東京なので、東京での展開はもちろん意識していました。地域との関係性を築くため、物理的に通いやすい場所という視点もありました。その中でいろいろ調べていくうちに、ピンときたのが奥多摩だったんです。
奥多摩は東京の水源地で、町全体が国立公園でもあるほど自然が豊か。東京で暮らしながらずっと知らなかったんですが、東京都の10分の1は奥多摩町が占めるんですよね。そんなに大きい町が都内にあったんだ!との驚きもありました。
さらに「水」も大きな理由になりました。
たとえば、災害時には「まず水の確保を」と言われますよね?それほど水は重要なもので、日々の生活にももちろん欠かせません。僕らはいま、当たり前のように水を使っていますが、それはダムのおかげです。ですがダムには、建設や水の流れで生態系の一部を崩してしまう負の側面もあります。
ダムを実際に見たこともないのに、命に直結する水を何の不安もなく使っているモヤモヤ。何かを失いながら水を思う存分使う生活。考えると何だか気持ちがスカッとしないところがあったんです。
そこで連絡したのが、奥多摩に住む以前からの知り合いであり、「TOKYO SAKURAMASU」の代表でもある菅原さんでした。
そのときは近況報告がメインでした。ただ、話の中で「こんなビジョンがある」とお伝えしたら、「とりあえず一回会いましょう」と。奥多摩の自然に癒されに来てくださいと言われて。仕事とは関係なく、ふらっと遊びに行く感覚で会いに行ったんです。
菅原さんは奥多摩で林業再生の仕事に取り組みながら、趣味の釣りにも力を入れていて。釣りコミュニティのSNS「アングラーズ」の公認釣り人であるアングラーズマイスターにも選ばれています。
このプロジェクトは、自然との共生の象徴として東京でサクラマスを復活させ、地域経済の活性化の起爆剤となることを目指しています。
サクラマスは鮭の仲間で、川で生まれる魚です。水質が良く、水量が安定している川に生息していて、以前は東京でも見られたと聞いています。そのサクラマスをここ奥多摩で復活させ、コミュニティを活性化させながら地域全体を盛り上げていく。それが大きなテーマです。
いえ、地域のあり方や環境の話をしているうちに自然と出てきたんです。
サクラマスは海に移動する個体で、2~3年回遊し産卵するときにまた川へ戻る。鮭と同様のサイクルで生きているのですが、ダムによって川へたどり着かない個体も。もちろん「魚道」という魚が通る道は作っているものの、うまく機能していないところがあって。
じゃあサクラマスを復活させるには?何が必要?と考えていくと、環境保全につながってくるんですよね。
川をきれいにして水質を改善する。そもそも個体が少なくなってきているから、全体の数を増やさないといけない。水質の点から考えると山から水が湧くので、山の管理が必須になる。
課題は山積みだけれど、ひとつずつ着手して進めていけば、サクラマスが復活するかもしれない。もし復活したら、サクラマスがきっかけとなり奥多摩へ人が来る。その先には、たとえば養殖をして、地域の産品になる可能性もある。そうなれば飲食店や宿泊施設も必要になり、人が集まってくる。
ブレストの中からそんな考えが生まれ、サクラマスが大きなキーワードになったんです。
そうですね、大きなイベントだと毎年3月に実施している稚魚の放流が挙げられます。11月には卵の放流も行っています。
直近の目標は「サクラマスが生息する環境をつくる」こと。
放流は地域や人を巻き込む点からも、個体数を増やす点からも重要だと考えています。これらのイベントを通して川の整備や、森の管理の仕方を広めてもいて。この活動が多くの人に知られて、企業の方に協賛いただいて……と輪をどんどん広げていけたらと考えています。
ハイドロフラスクさんは特別協賛として、活動にご協力いただいています。「ボトル1本購入で稚魚10匹放流」というユニークな取り組みも実現できました。
実は当社のクライアントワーク事業の中で、偶然ハイドロフラスクさんとのご縁があって。
ハイドロフラスクさんはアメリカ発のブランドで、サステナビリティを重視しています。日本でもサステナブルな活動を、積極的に行っていきたいとのお話を伺ったんです。
打ち合わせを重ねていく中で、ふと思いついたのは「ハイドロ」という単語。ハイドロには「水」という意味があり、「TOKYO SAKURAMASU」とリンクするものを感じました。そこで僕らの取り組みについてお話ししたところ、ぜひ一緒に取り組んでいきたいと言っていただけて。方向性がいいタイミングで一致した瞬間でした。
ご縁とタイミングがばっちりでした。ご縁と言えば協力いただいている、奥多摩のクラフトビール醸造所「VERTERE(バテレ)」さんもですね。
現在僕と一緒に活動しているメンバーが、以前奥多摩で働いていたんです。当時の勤務先を退職すると挨拶に来てくれた際、手土産に持ってきてくれたのがバテレさんのビールで。すごくおしゃれで印象的でした。
その後、東京サクラマスの活動を展開するにあたり、「地元のクラフトメーカーがあるから声をかけてみたら」とお繋ぎいただいたのがバテレさんだったんです。
奥多摩、活動メンバー、水と断片的だったピースが、一度にはまったような感覚でした。すぐに代表の鈴木さんをご紹介いただき、僕らの考えや活動内容をお話しして。VERTERE × Hydro Flaskのカスタムボトル制作が決まったときはうれしかったですね。
はい。奥多摩町でのイベントが少しずつ浸透していく中で、「もう少しカジュアルにこのプロジェクトに関われるイベントや活動がないか?」という声をいただくことも増えてきました。
そこでVERTERE × TOKYO SAKURAMASUのコラボレーションクラフトビールを、7/18(金)〜19(土)に東京のど真ん中・丸の内で行うことにしました。
ビールを1本ご購入いただくと、 TOKYO SAKURAMASUを通じて稚魚1匹の放流支援に繋がります!
そうですね。奥多摩に限定しているわけではないので、他の地域でもご縁があればぜひ、と考えています。実はちょうどいま、静岡市で新たなプロジェクトが始まりました。
僕も聞いて驚きつつ、ニヤリとしてしまったのですが「オクシズ」です。静岡県の山側、つまりは奥静岡エリアを略してオクシズと呼ぶそうで。「奥」に縁があるなとつくづく思っています。
中心となる舞台は廃校です。もとは小学校だった建物を利活用しながら、地域活性化につなげるのが今回のミッション。山の麓に位置していたり、横には川が流れていたりと奥多摩と似た環境でもあるので、横展開の第2弾としてぜひ成功させたいです。
そこにはアマゴという川魚が生息しています。これもまたサクラマス同様、海に向かう個体がいて、それらは「サツキマス」と呼ばれるんだとか。既に近くの漁協が稚魚を放流していると聞いているので、力をあわせてイベント化できるのではと思っています。
確かに社会課題の解決とビジネスとの両立は難しいと感じています。
ただ僕らはクリエイティビティを武器に、チャレンジしていきたいと思っています。営利企業として利益も追求しますし、社会課題の解決を本業以外で進めていこうというわけでもないんです。
その点は難しさであり、楽しさでもあります。
課題をクリアする企画やソリューションの提案は、すごく難しいものの非常にクリエイティブでもあると思っていて。僕らの発想力やクリエイティブさは、クライアント各社にもご期待いただけているのかなと思っています。
仲間やファンの輪を広げていくのも、実はとても難しいことなんです。
そんな「輪の広がり方」を象徴するような印象的な動画があります。ご存じの方もいるかもしれませんが、海外の音楽フェスで撮影されたワンシーンです。急に上半身裸になって踊り始める男性がいるんです。最初は周りから奇異の目で見られるんですが、楽しそうだからと一緒に踊る人が現れて。この2人目はマーケティング的に言えば、立派なフォロワー。その2人があまりに楽しそうだからとさらに人が加わっていくんです。そうなると1人だけで踊っていたときには白い目で見ていた人たちも、いつの間にか一緒になって……と輪が広がっていったんです。
この動画で言えば、絶対に必要なのは最初に踊る人。「〇〇したい」と盛り上がっても、実行するのは意外に難しいんですよね。実は熱量が一番大事なのかもしれません。
奥多摩でのリアルな空気感や、人との対話ですね。
現場に行ったり、そこで菅原さんや地域の方と話したり。もちろんSocial Plastikのメンバーも。特にメンバーとの話はとてもエキサイティングで、刺激を受けることもしばしば。イベントなど、参加者の皆さんの表情やお声はとてもモチベーションになります!
リバースビレッジ構想を実現したいですね。マイクロコミュニティでいろいろとチャレンジして、良かったものを各地域に展開していけたら。成功事例を社会に実装して、自分たちらしさを表現していきたいと考えています。
僕が学生だった頃は、SDGsなんて言葉もなくて、「エシカル」が通じるかどうかくらい。いま以上に、社会課題解決と経済活動が結びつくシーンは少なかったと思います。
ですがSDGsという共通の目標が現れて、「社会全体でめざすべきこと」と周知されました。誰でも「SDGs」と言ったら、何となくイメージできる。共通言語となったのはすばらしいことだと思っています。
第一線の企業ではSDGsは当たり前、それ自体が基幹事業になっている企業もあります。この現状をふまえると、僕らも次のフェーズへ移行しないといけないなと。価値観の浸透から、より社会実装にシフトするべきだと考えています。
すごくシンプルに言うと、僕らが大切にしているのは「かっこいいかどうか」。自分たちだけの利益を追求して、何かを犠牲にするのはかっこよくない。だからサステナビリティにもつながるんですよね。かっこいいスタイルを追求し続ける中で、より多くの人がファンになってくれたらうれしいです!
地域の未来を見据え、サクラマスの放流を通じたコミュニティづくりに取り組むSocial Plastik。
自然環境の保全と地域活性化を両立させるその姿勢は、きっとこれからも多くの人々の共感を呼ぶに違いありません。川に放たれた稚魚がやがて海へと旅立ち、再び故郷の水辺に戻ってくるように、この活動も地域に根付き、新たなつながりを生み出していくのではないでしょうか。
自然と人、人と人を結ぶこの取り組みが、より豊かな未来への架け橋となると信じて、これからも応援したいと思います!

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi