資料ダウンロード
rayoutはファンマーケティングを活用した
PRをご支援しています
閉じる

Takanashi
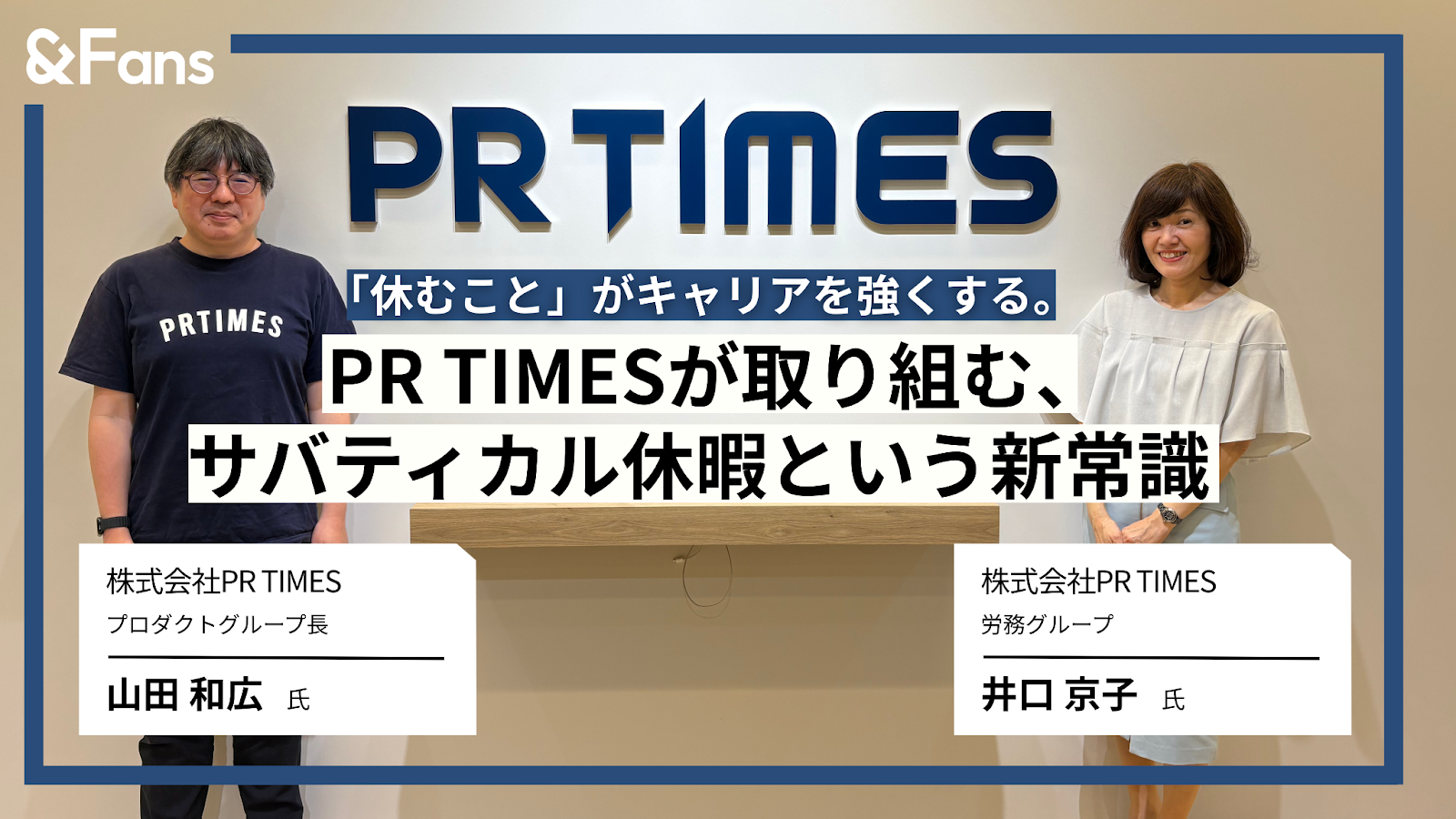

Takanashi
いつも頑張ってくれている従業員に、ゆっくり休暇を取ってもらいたい。……そう願っても、休暇取得者と業務引き継ぎ者の双方が納得できる仕組みを整えるのは難しいもの。「どうすればWin-Winな制度がつくれるのだろう」と頭を悩ませていませんか?
こんにちは、&Fans編集部の小鳥遊です。&Fansでは、熱狂を生むさまざまな企業や個人のストーリー、それらの考えに紐づくマーケティング概念などを紹介しています。
今回は、国内最大級のプレスリリース配信サービスを提供する「株式会社PR TIMES」が導入した「サバティカル休暇制度*」について取材しました。
働き方改革の一環として休暇制度を見直す企業が増えるなか、独自のサバティカル休暇制度を導入した株式会社PR TIMES。連続23日以上の有給休暇の取得に加え、業務引き継ぎ者に賞与を支給することで、「休暇取得者」と「引き継ぎ者」の双方に配慮した休暇の仕組みを実現しています。
今回は、先進的な制度がもたらす「従業員へのポジティブな効果」について、施策担当者の井口さんと、実際にサバティカル休暇を取得した山田さんに話を伺いました。
*サバティカル休暇制度:従業員に与えられる法定休暇ではない特別長期休暇制度のこと。一定期間勤続した従業員が、自由な目的で休暇を取得できる
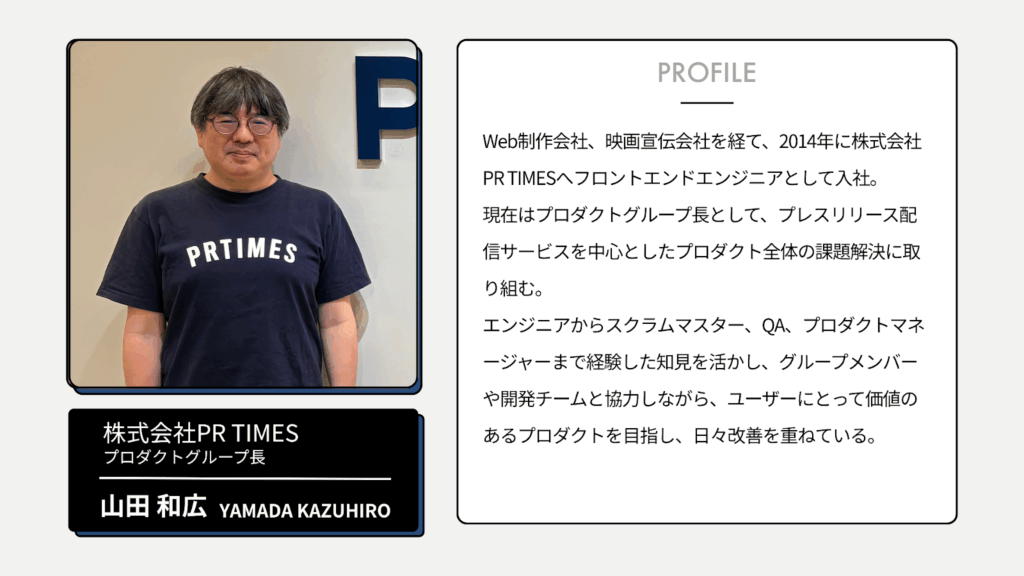
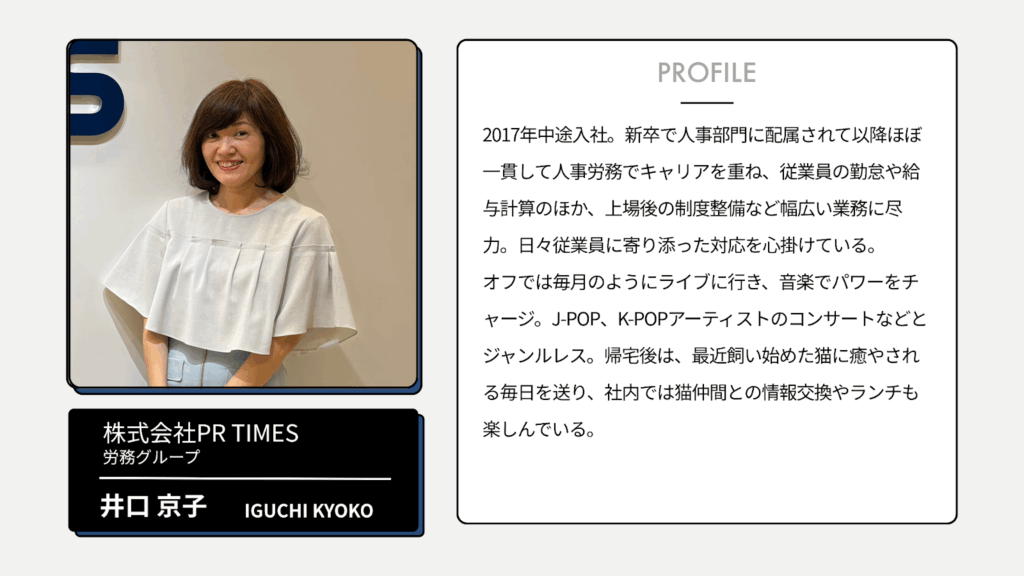
目次
当社はプレスリリース配信サービス「PR TIMES」を基幹事業として展開する企業です。そのほか、タスクプロジェクト管理ツール「Jooto」や、カスタマーサポートツール「Tayori」などのSaaS事業も展開しています。「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」をミッションに掲げており、これらの事業を通して“行動者”を支えることを目指しています。

おっしゃるとおりです。「行動者を支えること」に加え、「物事を決断した人を全力でサポートする」という当社の文化を体現する制度になります。サバティカル休暇制度の利用を決断した社員を、他の社員が背中を押す。背中を押した社員が、次は支えられる立場になる。そんな“行動者の支え合い”の循環が生まれる制度になります。
当社には創業時から尽力してくれているメンバーが数名在籍しています。そんな社員たちにまとまった休暇を取得してもらい、今後の人生・キャリアを考えてもらいたいと思ったからです。休暇のなかで、普段行けなかった場所や景色を見てもらい、これまでやこれからのキャリア・人生を見つめ直す機会にしてほしいと思っています。そして、それらの体験を復帰後の仕事にも循環してほしいと思い、サバティカル制度を導入しました。
そうですね。私自身、労務の業務を通じて「長期休暇を取ってほしい」と勧めても「生活がかかっているので難しい」と答える社員を多く見てきました。しかし、当社のサバティカル休暇は有給扱いのため、金銭面を気にする必要はありません。また、サバティカル休暇からの復帰時にレポート提出を求める企業も多いようですが、当社では不要としています。とにかく完全に社員の意思に任せ、純粋にそれぞれにとって特別な時間に過ごしてもらえる設計にこだわりました。
課題となったのは、休暇を取る社員の引き継ぎ業務です。休暇対象者は在籍7年以上の社員(初年度のみ10年以上)なので、勤続年数が長い分、担当業務も多岐にわたります。その業務を誰が担い、どうすれば不平不満なく引き継いでもらえるのか、頭を悩ませました。
業務代替者は、上長と人事部門が相談のうえで選定しています。さらに、引き継ぎを担う社員には5万円の賞与を支給する仕組みを設けました。サバティカル制度を導入している企業は多く存在しますが、賞与支給の仕組みを設けているのは当社ならではの特徴だと思います。

ありがとうございます。金額が低すぎるとモチベーションにつながらず、逆に高すぎるとプレッシャーになりかねません。とにかく業務代替者に“気持ちよく”取り組んでもらえるよう、賞与額の設定はかなり慎重に行いました。また、休暇取得者にとっても、有償であることは、心置きなく仕事を任せられる要素になっていると思います。
ありがたいことに、今のところ不満の声はあがっていません。むしろ前向きに受け止めてくれる社員が多いと感じます。実際に「上長の業務を代替したことで、各シーンでの仕事の進め方を理解できた」や「まだまだ自分は会社や周囲に守られていることに気づいた」など、新たな学びや発見につながったという声も寄せられています。導入当初は休暇取得者への効果を重視していましたが、結果的には業務代替者にとってもプラスの効果をもたらすことが分かり、予想以上の成果につながりました。
とても前向きに受け止めてもらえました。普段は帰宅が遅い日もあり、数日の連休しか取得したことがなかったので、家族にとっても新鮮だったようです。「23日間も休めるなら、色々なことに挑戦しよう」と話が広がり、平日にはなかなか行けなかった旅行や映画鑑賞などを楽しみました。
もちろん不安はありました。普段グループ長として業務上の判断を担うことが多いため、その役割をメンバーに任せることで負担をかけてしまうのではないかと心配で……。

そこで、自分がどのような基準で判断しているのかを改めて言語化し、マニュアルとしてまとめました。その結果、メンバーの負担を軽減できただけでなく、判断基準を理解してもらえたことで、より主体的に動いてもらえるようになったと感じています。メンバーにとって学びの機会になったと思いますし、私自身にとっても「部下の成長のためには、信じて任せることが大切だ」と気づくきっかけになりました。
確かに、社会人になってから1ヶ月近く休んだ経験がなかったため「こんなに長い期間休暇を取って無事に復帰できるのだろうか?」という不安はありました。ただ、会社が設けてくれた産業医面談を実施したことで、比較的スムーズに復帰できたと思います。
はい。産業医面談では、休暇中の過ごし方や復帰後1週間の仕事への取り組み方についてアドバイスをいただきました。海外の研究結果から「サバティカル休暇は取得前の準備が重要」ということが明らかになっているそうで、会社から産業医面談や休暇時の心得動画の視聴を推奨されました。23日間の休暇は初めての経験でしたが、休暇前のフォロー体制が手厚かったおかげで、安心して休暇期間を過ごし、スムーズに復帰できたと実感しています。
お客さまとの理解や接点を深めるきっかけになりました。当社では、会社で使用する備品類を「PR TIMES」に掲載されたお客さまのプレスリリースを参考に購入する文化があります。その延長で、サバティカル休暇中の社員がプレスリリースをもとに、普段行けなかったイベントや施設に足を運ぶことで、お客さまとの関係をより深める機会につながっていると感じています。
そうですね。お客さまへの理解や接点を深める取り組みは、会社が強制しているのではありません。リフレッシュした環境に身を置いているから、自然と湧き上がる感情なのだと思います。サバティカル休暇を経験した社員は、次に誰かが休暇に入るときも快く送り出せるはずです。そうした“行動者同士の支え合い”が循環していくことで、事業面でもさらに良い効果が得られることを期待しています。
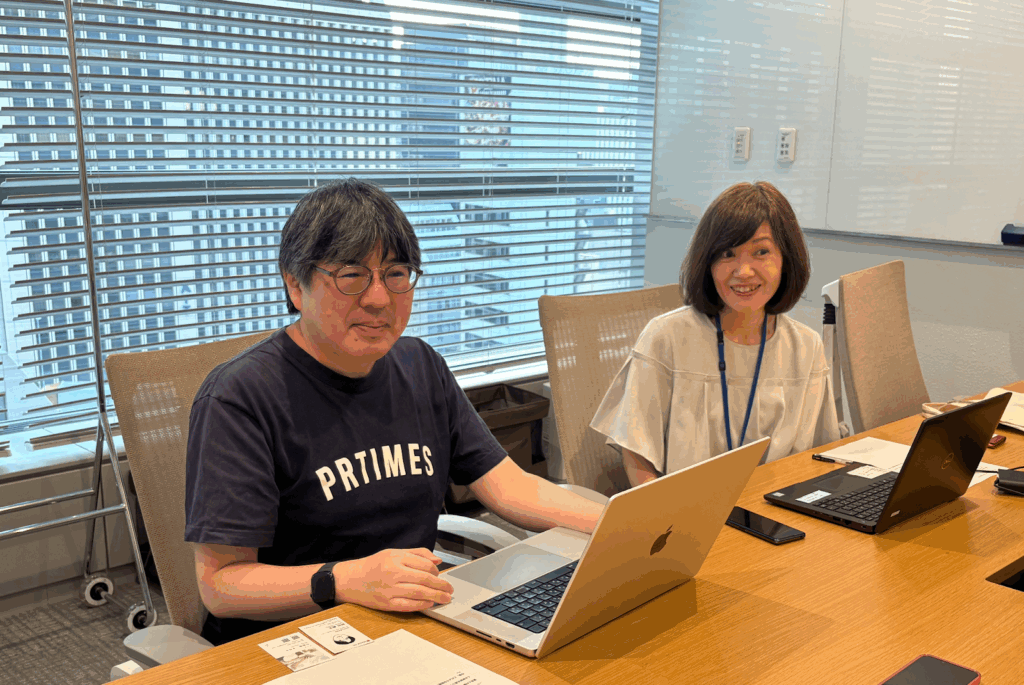
当社の経験からも言えるのは、長期休暇制度の導入は想像以上にハードルが高いということです。だからこそ、まずは“リフレッシュ休暇”として1週間程度の休暇制度から始めてみるのがおすすめです。また、これまでに「どうしても短期留学に挑戦したい」「無給でも良いから長期間休む機会がほしい」といった社員の声もありました。そうした希望を叶えられる仕組みを設けることも、社員への貢献として大きな価値を持つ取り組みになると思いますので、ぜひ検討してみてください。
「長期休暇を取れるなら、趣味や勉強に時間を充てたい」と考える社会人は多い一方で、まだまだ「長期休暇=迷惑をかける」という風潮が根強いのも事実です。
しかし、休暇取得者と業務代替者の双方が“気持ちよく”感じられる仕組みをつくることができれば、こうした風潮も自然と変わっていくのではないでしょうか。
その風潮の改善に大きく貢献している、PR TIMESのサバティカル休暇制度。従業員エンゲージメントの向上に寄与することで、「他人に勧めたい会社」「退職したくない会社」と感じてもらえる“副次的な効果”も期待できそうです。
▼「従業員にとって、自社はどう評価されているのだろう……?」と気になる方は、こちらの記事もおすすめです。
従業員エンゲージメントの鍵を握るeNPS—企業成長を加速する新しい評価軸
取材・執筆:小鳥遊まゆか
編集:神谷周作

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi