資料ダウンロード
rayoutはファンマーケティングを活用した
PRをご支援しています
閉じる

Igarashi


Igarashi
こんにちは。&Fans編集部の五十嵐です。&Fansでは、熱狂を生むさまざまな企業や個人のストーリー、それらの考えに紐づくマーケティング概念などを紹介しています。
私は編集部として&Fansの運営を行う傍ら、運営元であるrayout株式会社にて広報を担当しています。
&Fansはマーケティング担当の方にも多くご覧いただいていると思いますが、マーケと広報、それぞれの”強み”と”限界”を感じている担当者や、兼務をしている方にこそ知ってほしいのが、「ファンを生む戦略的な連携」の力です。
マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが”共感”となり、”応援”となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?
今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。
目次
従来、マーケティングとは「市場創造のための総合的活動」、つまり製品やサービスを売るための活動と位置づけられていました。あくまでも主体は企業側。企業から直接生活者へ伝えていく、広告・宣伝の領域の認識でした。
しかし2024年、34年ぶりに公益社団法人日本マーケティング協会が定義を刷新し、共創的で持続的な視点が追加されました。「顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである」と定義されています。この考え方はかなり広報寄りなんですよ。発信すれば良いというのが大前提になっていましたが、顧客や社会を意識するということに刷新したのがポイントです。
一方広報領域は、企業の製品やサービスなど企業活動全般を、メディアを通じて、客観的に情報提供することが基本となります。“メディアを通じて”というのが、マーケと広報の大きな違いなんですね。私たちの世界ではあくまでもメディアを意識する。そのバックボーンとして、生活者などのステークホルダーがいます。
はい、マーケ担当の皆さんも広報を知ることで、シナジー効果が期待できます。ちなみに、私は年間200社ほどコンサルしていますが、約4割の企業はマーケと広報を兼務されていて、その比率は年々増加しているんですよ。
また最近はSNSの台頭で、個人でも情報発信ができる環境となり、メディアと個人のボーダーレス化が進んでいます。noteは個人が発信するメディアのようなものですからね。現代では新聞やテレビは、オールドメディアだと見られがちですが、SNSが発達してもメディアの役割はまだまだ重要性が高く、影響力があります。広報から見ても大切な相手です。
高くなりつつありますが、MAXではないといったところでしょうか。
まだまだ日本の情報環境はメディア主体です。紙からデジタルにシフトしていますが、コンテンツそのものは変わらないです。とはいえメディアが激変しているので、広報の皆さんはリサーチしていかないといけませんね。週刊誌等の紙メディアがなくなってしまう……いわゆる*2027年問題と言われている現状がありますから、ここ4-5年で相当変わってくるのではないでしょうか。でも、コンテンツそのものは40-50年前から今まで変わってないんですよね。
*2027年問題:週刊誌などの紙メディアの廃刊が加速すると予測される問題
大前提として会社の製品やサービスの特徴や強み、他社との違いを伝えることは必須です。インフルエンサーやYouTuber等の著名人ユーザー、専門家のコメントなどを意識して伝えるとインパクトがあります。
加えて重要なのは、記者や編集者に対して、商品・サービスを極力体験していただくこと。マーケ担当者にはあまり馴染みがないと思いますが、広報にはプレスリリースという、商品やサービスの情報を記者さんにお伝えする書面があるんですよね。ただ、テキストで記者さんに伝えても伝わりきらないこともあります。例えばスマホが商品だとしたら、感触や重さ、サイズ、画面のクリアさ、通信環境の良さなどを体感してもらうことで共感が生まれます。この共感が、すごく大事なんですよね。皆さんも、心が動く体験があったら誰かに伝えたくなりませんか?共感が広がれば、広報もマーケもだんだん活動が活発になって、情報に厚みが出てきます。
もちろん数値などの客観的な情報も大切ですが、触って試してもらうということがより重要です。メディアの方に体験してもらうために、私たちは「メディアキャラバン」ということをします。商品を持って、新聞社さん、出版社さん、テレビ局さんと回って、商品を試してもらって、直接質問を受けるんですよ。そうするとかなりインプットしていただけるんです。メディア関係者もファンになって頂くと、報道の量が増えたり、また商品・サービスの理解者として報道の質も高くなります。メディアは、読者=消費者の代表であり、消費者の共感を生んでいきますから。
また、新商品や新サービスの発表があれば、記者説明会を行うのも良いです。メディアを会場にご案内して体験していただく。マーケティング寄りの施策として、インフルエンサーの方を呼ぶのも手です。
そうですよね。私にもよくそのようなご相談があります。コストもかかるし、記者もそんなに大勢いらっしゃらないのではないかと。でもそんな大規模な準備は必要ないんです。自社の会議室等のちょっとしたスペースに、5人くらいお呼びするという形でも全く問題ありません。広報もマーケもですけど、「まずはミニマムでやってください」とよく言うんですよ。予算的にも、作業効率的にも良いですから。
toBであろうとtoCであろうと、変わらないと思います。例として、ターゲットの方々を集めて勉強会を開き、サービスを触ってもらうというのもありです。ストレートに「このサービスや製品を買ってください」ということではないので、ハードルは下がりますよね。マーケ的な側面もあるので、マーケチームと予算を折半できるかもしれません。それに、「一歩先のトレンドを勉強できる企画なら参加したい」というメディアやインフルエンサーもいらっしゃるんですよ。
昔はこのような勉強会も「顧客だけでないとダメ」等という型があったのですが、今はないです。先述したプレスリリースだけですとニュース性としては少し低いので、逆に記者さんはそういう独自情報が欲しいんですよ。とある雑誌の編集長も、「プレスリリースをそのまま書くということはやりませんが、プレスリリースに付加価値があって、それを追跡して取材するというアクションはある」ということを明確におっしゃっていました。勉強会や記者説明会などの企画をうまく設定して、あくまでもプレスリリースは入口であると考えると良いです。
私はIT系サービスの企業とも、何百社とやりとりをしていますが、皆さん自社サービスの説明から入っちゃうんですよね。体験してもらうということも大切ですが、でもそこからではなく、まずは社長ってどういう人なのか?エンジニアの方のプロフィールは?という情報をインプットしてもらうことも効果的です。サービスへの想いやカルチャーみたいな部分が、ファン作りには大事だと思うんですよね。
どんなに機能・特徴が素晴らしいと言っても、大抵はレッドオーシャンです。その中でどのようにリーチを取っていくかと考えると、それは”人”なんですよ。カリスマ性というのかな。例えばもしもエンジニアの方がスゴい人であれば、それは全面に推してタレント化すべきです。それこそ、”推し活”ですよ。これからの時代、すごく必要になってくると思います。
そういう表現だと分かりやすいですよね。テクニカルな話ばかりしても、多くの方にその差は伝わりにくいです。何が差を生むかというと、やはり”ファン”ですよね。「触ってみたけどなんかこのサービス良いよね」「この開発者の人、好きなんだよね」そういうコメントが広がっていくのがベストです。
これは不思議なんですが、皆さん当たり前だと思っている情報が、実はすごくインパクトがあったりするんですよ。客観的に見たら注目すべき財産・ネタが埋もれていることがあります。特に人の情報というのは、新しくも古くもどちらでもいいんです。その方が今までどんな仕事をしてきたのか、苦労を重ねてきたのか……”生き様”という表現がいいのかな。例えば、スポーツ選手は、生き様を知ってファンになる方もいますよね。社員の人生を掘り下げていただけると、何か出てくるのではないでしょうか。
多くの人に語られるためには、やはりストーリーが重要で、根底にあるのは“人”です。その発信方法の一つがニュースレター。PowerPointやWordで作れる簡易なもので構いません。単なるプレスリリースではなく、会社全体の姿や各部署のキーパーソン、社長の想いなどをストーリー化し、メディアやステークホルダー、社内に届けます。まずはnoteで発信し、それをまとめてニュースレターにするのも効果的です。
会社の規模に関係なく、やはり経営トップ、社長さんの考えを発信していく事は大切です。起業したということは世の中にとって公器なことなので、社会的に発信していく意識は重要になってきます。また、小さい会社でも営業だったりマーケだったり、いろんな部署があるわけですから、各部署からトピックスを集めても良いですね。
そうですね。プレスリリースだと、タイトルやキーワードに悩んだりする方も多いと思いますが、ニュースレターはあくまでお手紙です。メールではなくあえて郵送で送って、定期的に届くということを認識してもらうのも手ですよ。意外と、送り続けていると問い合わせが来ることもあります。「この社長さん面白そうだからインタビューさせてください」とか。今の時期はちょうど、「夏枯れ」と言われている記者さんがネタに困る時期なので、暑中見舞いみたいな感じで夏にお送りするのも良いと思います。
タイミーの事例をお話します。私はタイミーの立ち上げ時に広報のお手伝いをしていたのですが、最初はメディアも疑心暗鬼だったんですよ。「こんなことがビジネスになるのか」と。それでも私たちはプロとしてなんとかしなくてはいけない。その時感じていたのは、社長さんの熱量なんですよね。話し方にすごく熱を感じたというよりも、「このビジネスモデルは絶対世の中のためになる」という、確かな理念の元に起業されているという想いがとても感じられました。何が発信できるかって、その想いしかないと。そこで、「私はこういう人間です」という社長さんのプロフィール資料をしっかり作りました。そのような「共感してもらうためのストーリーづくり」が発信の際には重要です。
ベンチャー企業×ファンと言うと、投資家に”ファン”になってもらう、資金調達もある意味そうですよね。資金調達が出来た際は是非、プレスリリースを出してください。信頼がある会社であるというアピールになりますし、報道を獲得できればさらなる融資を呼び込める可能性があります。具体的にどのようなプレスリリースを作ると良いかは、是非拙著を読んでいただくとわかりやすいです。
経営層には、大きな報道番組や有名新聞への露出を重視する人もいれば、その価値を理解せず営業だけに注力する人もいます。しかし、会社を知ってもらう重要性は共通です。私がコンサルで伝えているのは、「会社は公器」という考え方。社員、株主、取引先に対し情報を開示することは経営者の役割であり、内容の多少はともかく、最低限の開示は欠かせません。
危機管理の視点でもそうです。会社で不祥事が起こったら矢面に立たされるのは社長さんですから。攻めの広報だけでなく守りの広報もあるということも知っておいていただきたいと思います。
はい。中には、悪い報道を書いている記者さんを優先して会うということをしている企業もあります。普通はそんな勇気ないですよね。これこそ広報マインドです。マイナス報道の中でも、こちらの意図するものと違う情報があるかもしれないので、記者さんと顔を合わせて説明をする。そこまでされたら、記者さんも逆にちょっとその企業を好きになりませんか?顧客に対しても同じことが言えると思います。一緒にサービスを作っていくという感覚で、耳の痛い声もしっかり受け止めることで、サービスが良くなるだけでなくお客さまとの関係性を深めることにもなります。
そうですよね。私も敢えて評価の低い人のコメントを見たりします。広報やマーケの領域でも、ターゲットがどのように商品をリサーチしているのか意識すると良いですよ。
基本、企業や商品・サービスのファン獲得の方法は一致しています。マーケも広報も、自社のステークホルダーを設定して、ターゲットに向けて発信する情報取集→情報の選別(ネタづくり)→各部署での発信時期と方法→情報発信→結果確認→KPIに基づく振り返り・課題発掘の流れで回していきます。月に1、2回、マーケ・広報チームで定期的なMTGを行うと良いですね。
ぜひ双方が意識し合い、共感・応援される企業を目指していってください!

STEP1
情報取集

STEP2
情報の選別(ネタづくり)
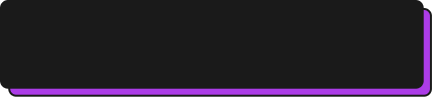
STEP3
各部署での発信時期と方法の精査

STEP4
情報発信

STEP5
結果確認
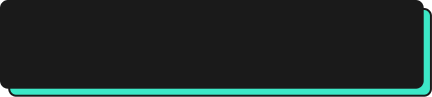
STEP6
KPIに基づく振り返り・課題発掘
今回三上さんとお話する中で印象的だったのは、単に製品やサービスの良さを伝えるだけでなく、「人」のストーリーや企業のカルチャーを発信することの重要性です。結局、情報を受け取るのも人であるということ。体験してもらうことも社員の生き様を伝えることも、人の心を動かすためのアプローチであり、心を動かすにはどんな施策が良いのかを考えることが、ファンを増やすヒントだと気付きました。
また、三上さんからお聞きした「会社は公器」という言葉。企業からの情報発信はファンを増やすだけでなく、ステークホルダーとの信頼関係を築くための責務でもあります。この視点を持つことで、広報活動がより戦略的で意味のあるものになるのだと感じました。
これから広報を始める方、広報の基本から知りたい方はまず、三上さんが執筆されている『広報のプロが教えるメディアのトリセツ―取材獲得への5ステップ』をお読みいただきたいです。私も拝読しましたが、広報としての考え方・基礎的な動き方だけでなく、記者さんの考えを詳しく知れるインタビューや具体的な事例も沢山載っていて豪華な一冊です。とても勉強になります!
また、弊社rayout株式会社でも広報・PR、マーケティング領域のお手伝いをしております。クリエイティブ制作、SNS運用、イベント等、愛される会社・サービスを作っていくための施策を幅広くご提案させていただきます!是非お気軽にご相談ください。
取材・執筆:rayout 五十嵐
編集:神谷周作

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi

株式会社ココナラの執行役員、竹下加奈子さんにインタビュー。スキルマーケット「ココナラ」の成長の背景や、ユーザーとの信頼関係の構築方法について詳しく紹介。信頼性確保のための取り組みや、今後の展望も伺いました。
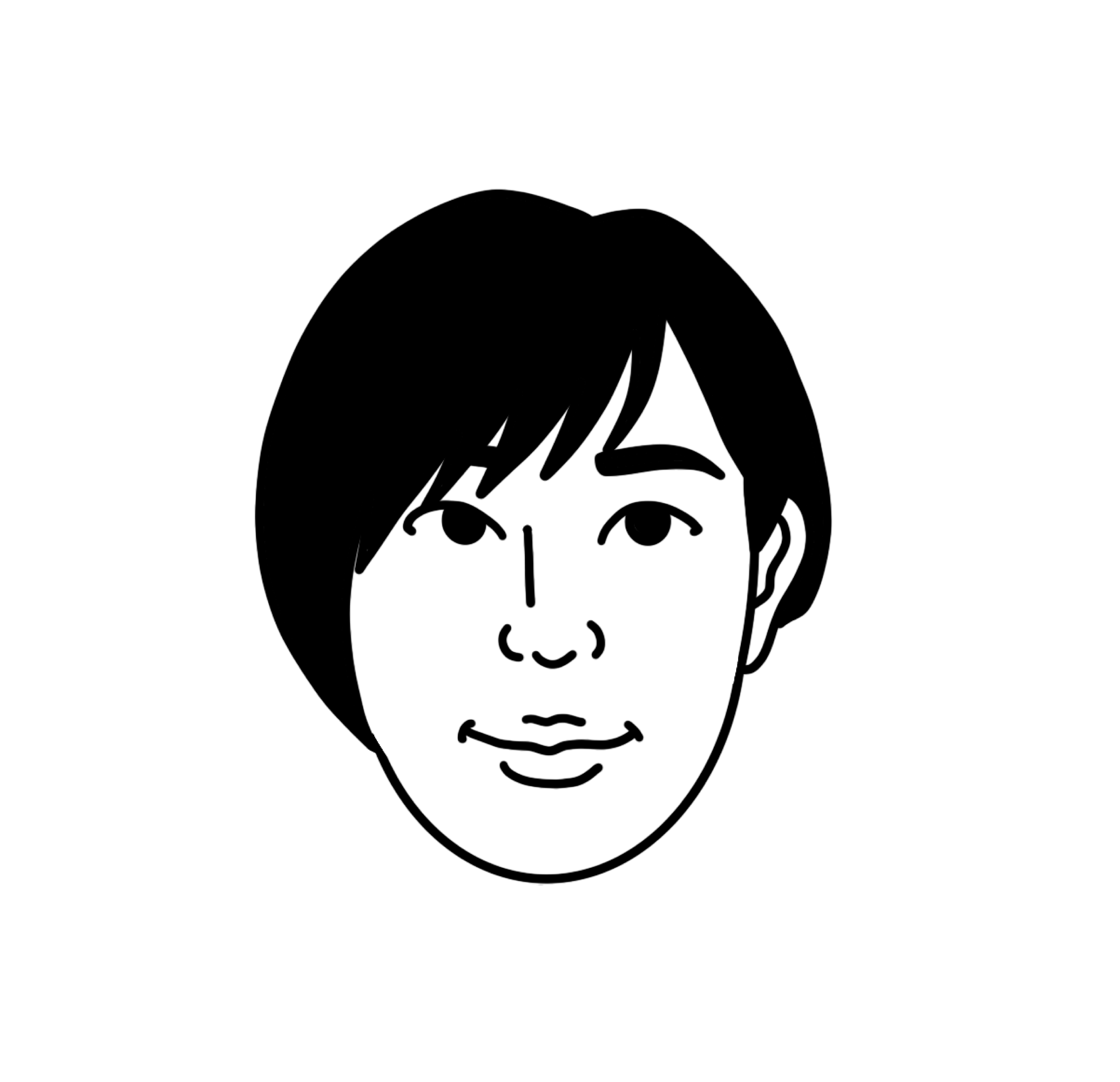
Matsui