資料ダウンロード
rayoutはファンマーケティングを活用した
PRをご支援しています
閉じる
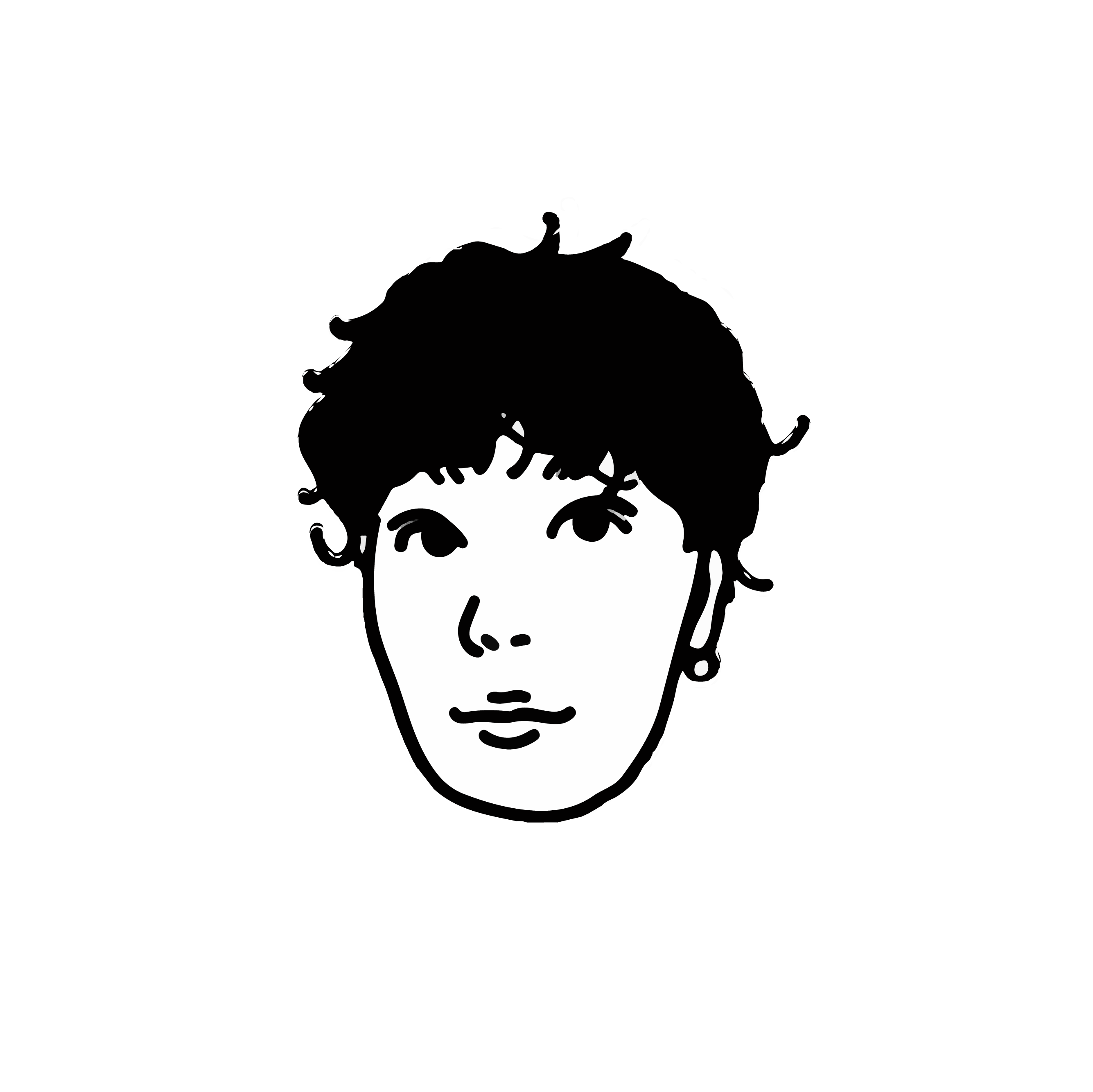
Shibashi

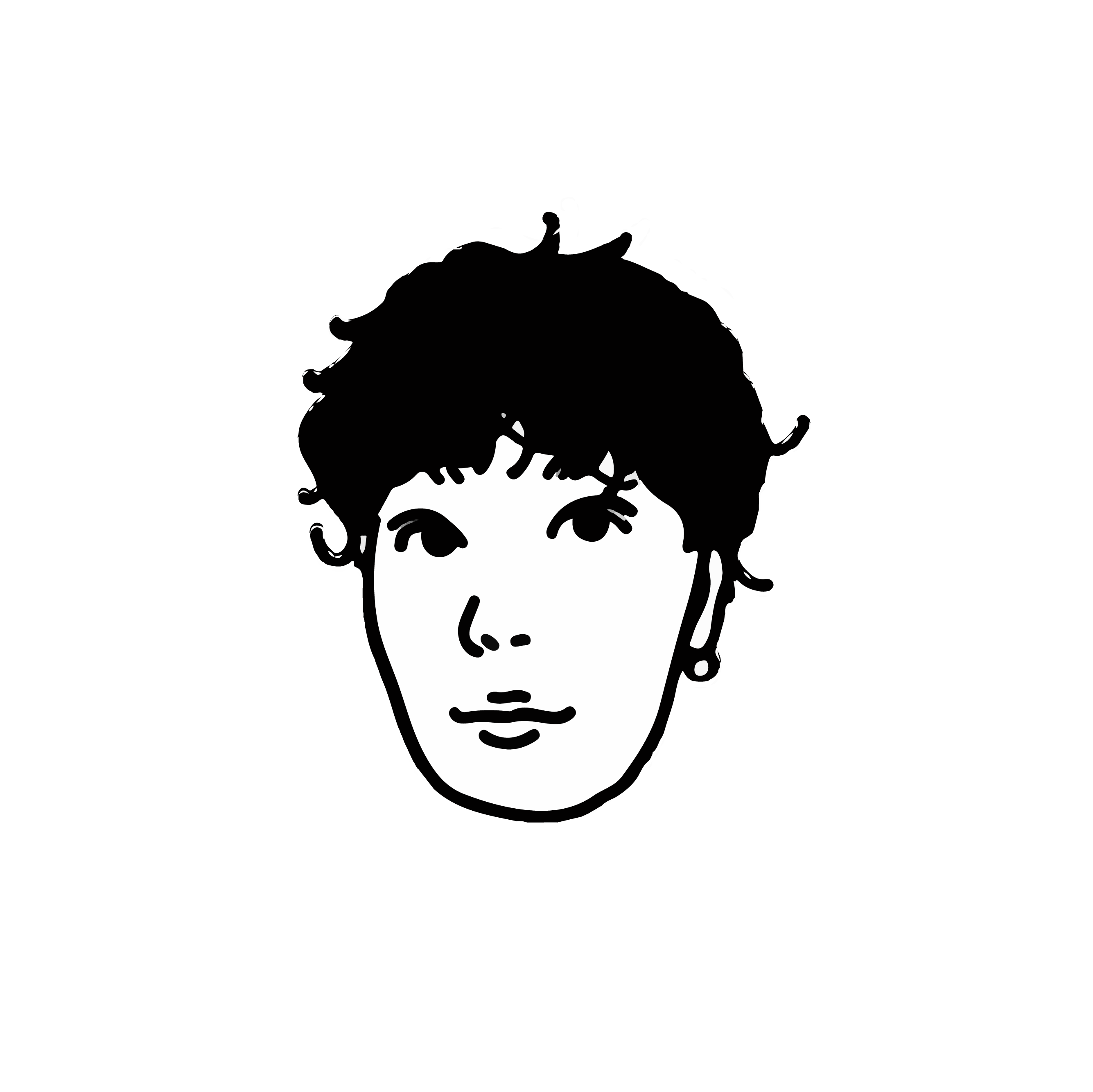
Shibashi
こんにちは、&Fansライターの椎橋です。
&Fans では、熱狂を生むさまざまな企業や個人のストーリーや、それらの考えに紐づくマーケティング概念などを紹介しています。
今回は有機野菜やオーガニック野菜を中心とした食材の宅配サービス「ビオ・マルシェ」を展開する株式会社ビオ・マーケットの取締役事業本部長の安本さんにお話を伺いました。
単なる食品販売に留まらず、生産者と消費者との交流に力を入れるビオ・マーケット。あえて難易度の高い有機農業にこだわる理由や、生産者第一を掲げる中でファンに支持されるその真相について探っていきます。
目次
有機農産物や加工食品の販売を行っています。自然に寄り添うことで日々の生活を丁寧に、自分らしく生きる「暮らしの真ん中にオーガニックを。」というテーマのもと、オーガニックな暮らしを農産物や加工食品を通してお客様に提案しています。
「安心で美味しいオーガニックを、特別な人だけでなく、求めるすべての人に届けたい」という想いで1983年に小さな八百屋からスタートしました。
創業者はもともと会社勤めのサラリーマンでした。当時は高度経済成長期真っ只中。経済が進歩していく一方で水質や土壌汚染が社会の中で問題視され、環境保全の意識が一気に高まってきた時代でした。
そういった背景の中、創業者は無農薬や有機肥料を使用して栽培している人々と知り合い、強い感銘を受けました。そして「街を耕す百姓になろう!」というスローガンのもと「買ってくれる人」と「つくる人」をつなげる事業を立ち上げる決意をしました。
生産者同士の品質を統一させることにかなり手こずったようです。例えば、同じトマトを生産していても農家が違うと大きさのばらつきが出たり、作業工程が違ったりと。規格や品質を統一させる地道なことからはじめていったそうです。
創業者の意志を受け継ぎながら、2001年からは取り扱う野菜全てを有機JAS認証を受けたものに統一させました。
有機JASの認証を受けるためには、農林水産省が定めた基準をクリアしないといけません。科学的に合成された農薬や肥料を使用していないか、遺伝子組み換え技術を用いていないか、環境負荷を低減する生産方法を採用しているか、など厳しいチェックが入ります。
一番の理由は取り扱う野菜に「有機JASマーク」が記載されるからです。国から有機JAS規格に認定されると「有機JASマーク」が表記されるようになります。このマークがしっかり表示されていると、それだけで消費者の方に「これは国に認められている安心した野菜」と信頼していただけるんです。
また、生産者の方には有機JAS認証という明確な基準を目標に作業をしてもらえるので「有機JAS規格」を見える化することは、買ってくれる人とつくる人の信頼関係を結ぶうえで、とっても重要なんです。

有機農業の世界は狭い業界ではあるので、生産者が「有機農業を取り扱ってくれる会社はないかな」と調べていただいた先に、私たちが現れてくる機会が多いんです。そこで私たちの理念に共感してくださる生産者との繋がりを得ます。
それから、知り合いの農家さんが「ビオ・マーケットの活動に興味があるみたい」と新たな農家さんをご紹介してくださるケースも沢山あります。設立当初から続く、人と人とのつながりによって、コミュニティーが広がっています。
「ビオ・マルシェの宅配サービス」https://biomarche.jp
中心となるものはやはり有機野菜ですが、肉や卵、調味料、衣類や化粧品も取り扱っています。環境に対して負荷の少ないものや、歴史ある技術を生活の中に取り入れることも我々が提案している「オーガニックな暮らし」のひとつだと考えているので。
週に1回発送される商品カタログからお選びいただいたものが1週間に1度のペースで届く流れとなります。
30〜40代の方が中心ですね。お子様に良いものを食べさせたいという考えをお持ちの方や、自分の身体に優しいものを取り入れたい、といった方がご利用くださっています。
最近では、シニア層にも注目してもらっています。食べる量が減ってきたけれど、その分こだわって、質の良いものを食べたい、という方たちが入会してくださります。重い荷物を運ばなくても良いという宅配配達ならではの点もプラスになっているようです。
電子でも行っていますが、昔からご利用されている方や、シニア層の方には紙のほうが馴染みがあるようなので、基本的に冊子のカタログをお送りしています。
めちゃくちゃ頑張って作っています。3、4週並行で常に企画やデザインが進んでいます。いつも6週先のものを作っていますね。
このカタログには品目紹介の他に、生産者の想いや、こだわり、お人柄を取り上げたコラムが掲載されているんです。これが会員の方にとても評判が良くて。コラムを読んだことで生産者の想いに共感し、「この生産者さんの作った野菜を買おう」と購入してくださる方が大勢います。生産者を応援してくださる方は定期購入のリピート率が高いんです。野菜の安全性、美味しさはもちろんですが、生産者の気持ちに共鳴できるかどうかが購入に至るまでの判断材料としてあるようです。長い人だと30年以上利用してくださる方もいらっしゃいます。ですので、カタログ制作にはかなり力を入れています。
原則、毎週同じ配送員がお届けをします。同じ顔ぶれだからこそ安心感を抱いていただけますし、会員の方とのコミュニケーションも生まれるので、様々な意見も伺えます。
「ビオ・マルシェ」のカタログの品目と比べると、本当に一部のものに限られますが、スーパーマーケットでも購入することができます。生活全てをオーガニックに切り替えるのは大変だけど、ちょっと興味がある、なんて気持ちを抱いてくださる方が気軽に買える場所として活用いただければと思っています。
オーガニック野菜は高いわりに美味しくない、といったイメージを持たれる方も現状としていらっしゃいます。有機野菜は化学肥料や大半の農薬を使うことができないので、その土地でその季節にあった野菜しか作れないため、どうしてもコストがかかってしまうんです。
しかし一方でオーガニックには、自然に近い状況下でつくられた「旬のもの」を食べられるという大きなメリットがあります。「旬のもの」は栄養価も高く、味も濃厚でとても美味しいんです。
現段階では、はじめから生産者やオーガニックな生活に興味を持ってくれる人たちを大切にしていくことが重要だと考えています。割合としてはまだまだ少ないですけれど、とことん親身になることが私たちにできることだと思っています。
定期的に生産者と直接つながれるイベントを開催しています。「ビオ・マルシェ」で販売している「かんたんみそセット」を用いてみそ作りを体験してもらったり、実際に畑に出向いて収穫体験をしていただくような機会を提供しています。このイベントは実際の製品を取り扱っている生産者の方に主導していただくようにしています。生産者と触れ合って生の声を聞いてもらうことで、作り手の想いを強く感じ取ってもらえるように場になってもらえれば、という考えからです。
他にも、生産者と会員の関係をより密にする為に、産地から旬の野菜や果物を直送するサービスも行っています。
私たちが取り扱っている野菜や果物は、基本的にはその時期にできたものを全国各地からお送りするので、同じ品目でも季節によって産地も生産者も異なります。例えば、にんじんなら冬から春は九州、夏から冬に信州、北海道といった具合にシーズンによって違う産地のものが送られてきます。しかし直送にはそれがありません。推していただいている生産者の農産物がダイレクトにお客様の元へ届くので「好きな生産者を応援したい」「この生産者の野菜が食べたい」という気持ちに応えられるような仕組みを作っています。
ありがたいことに、会員になってくださる方も多くいらっしゃいます。知り合いから勧めてもらったものの宣伝効果はとても強いですね。知人に紹介してもらったから「ビオ・マルシェ」の会員になりました、というケースは非常に多いです。
そういった方々は、持続してサービスを利用してくださるように感じます。
有機農業を行っている生産者がいないことにはビオ・マーケットは成り立ちません。そんな生産者の方々を大切にしていくことが「ビオ・マーケット=オーガニック」という認識作りのためには必要です。
そのためには、営業や仕入れスタッフも含め、できる限り生産者の産地に訪問し、現状を把握して継続的にお取引してもらえるようサポートを行っていくことが大切だと思っています。
気候変動、後継者不足、高齢化は、生産者に常に付きまとう課題です。
私たちは年に2回、生産者一同、弊社の本社がある大阪にお集まりいただき、ビオ・マーケットの方針を改めて確かめ合う機会を設けています。この会合で生産者の方々には、品目の情報を交換してもらったり、後継者を紹介しあってもらうなど、つながりを作っていただいてます。設立時から大切にしている人と人をつなげるしくみを、今でも大切にしています。
オーガニック業界での存在感をさらに高め、有機農業や加工品の取扱量で日本一を目指していきます。そのうえで大切になっていくことは、やはり生産者との絆です。生産者の皆さんがより活動しやすく、有機農業が増えていくしくみを作るためにも販売を伸ばしていくつもりです。
生産者を家族のように捉え、二人三脚で歩んでいくビオ・マーケットのガバナンスは、顔を合わせずにシステマチックに進んでいく現代のシステムとは真逆です。
しかし「人と人とのつながり」を大切にしているからこそ、消費者は心から信頼してビオ・マーケットでの購入を積極的に行うのでしょう。
まずは気軽に、ビオ・マーケットが卸しているスーパーマーケットの野菜を買ってみることから、オーガニックライフを始めてみてはいかがでしょうか。
取材:rayout髙柳凌人
執筆:椎橋萌美
編集:神谷周作

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi