資料ダウンロード
rayoutはファンマーケティングを活用した
PRをご支援しています
閉じる
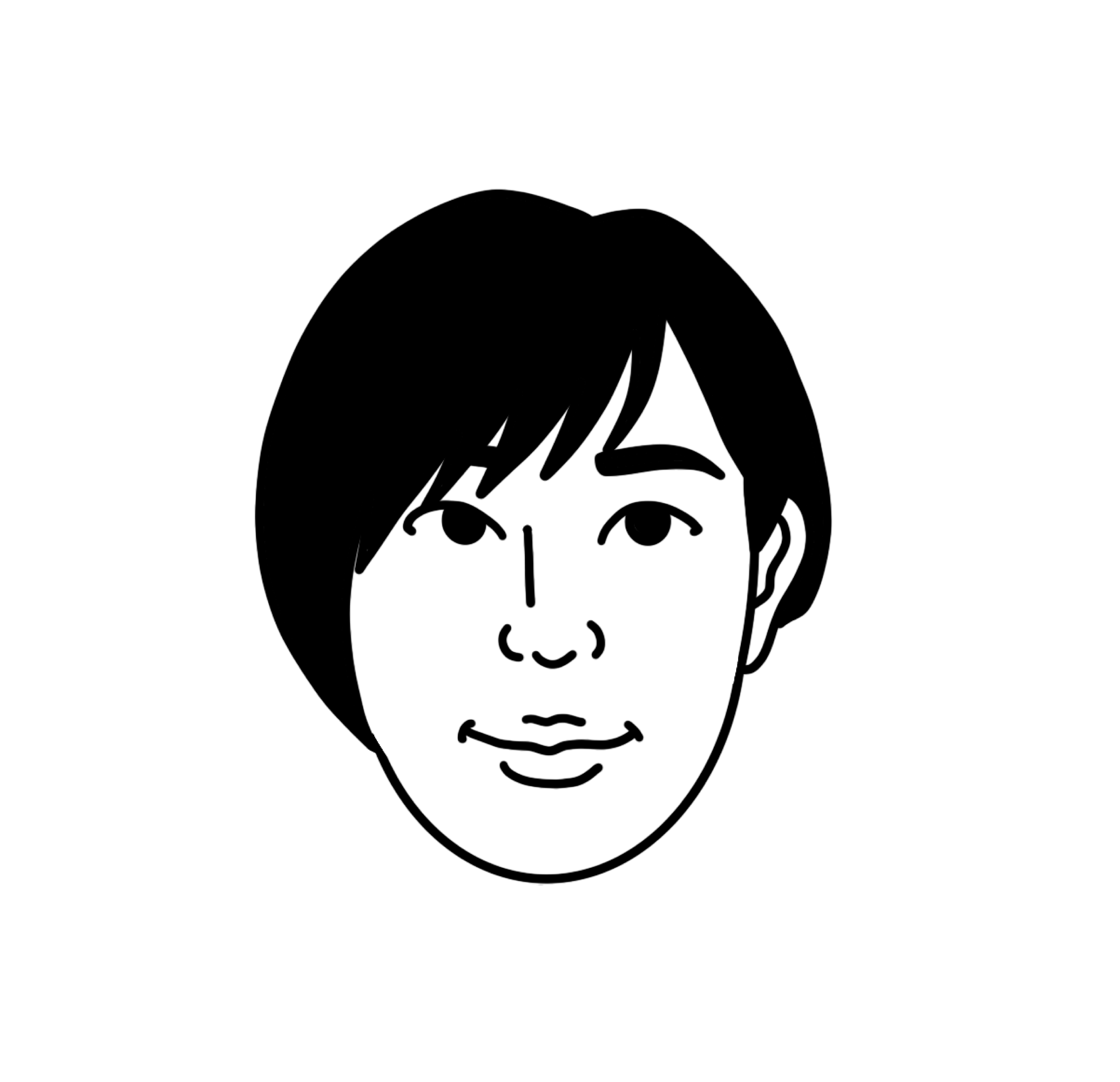
Matsui

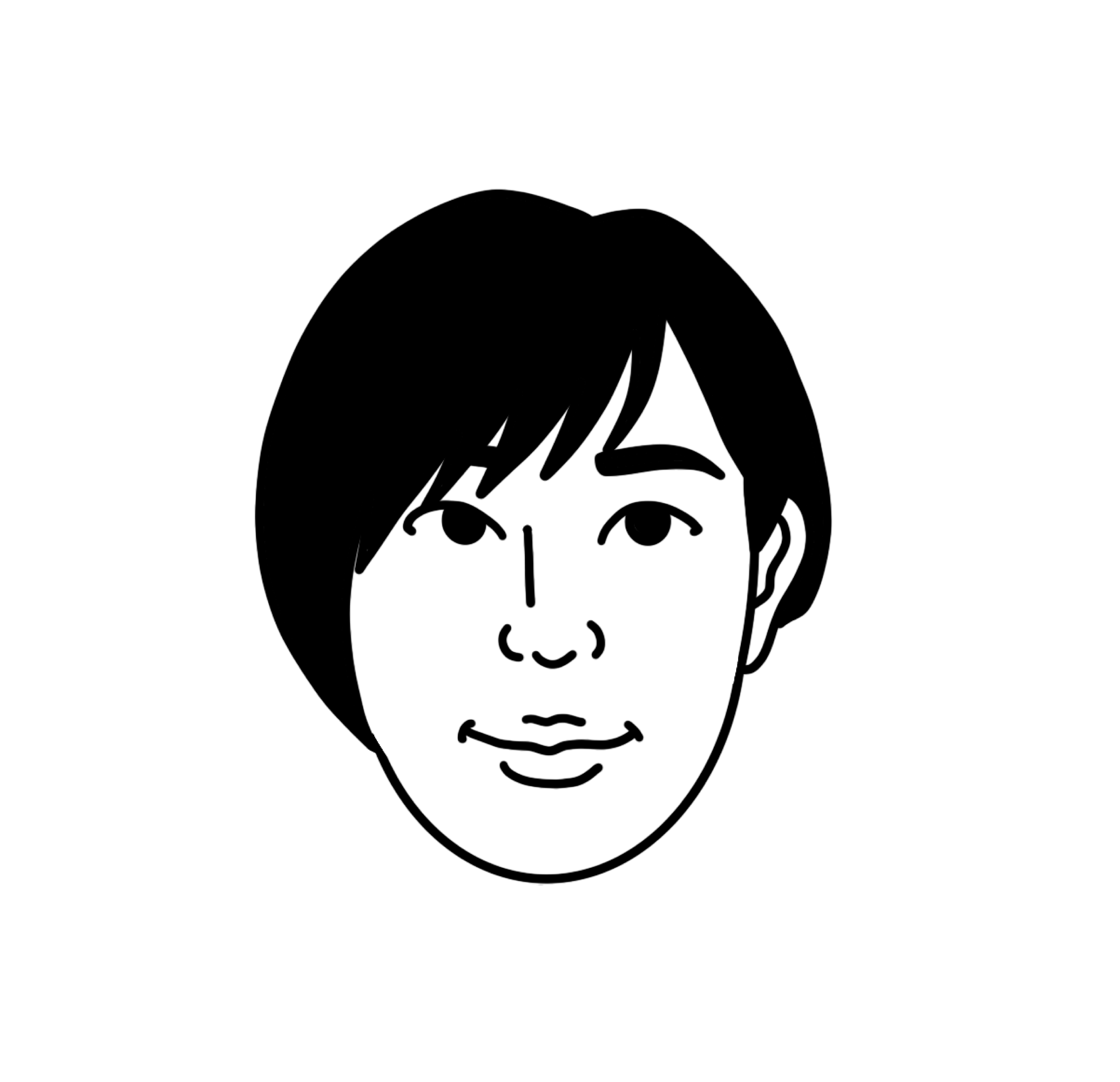
Matsui
こんにちは、&Fansライターのマツイです。
&Fansでは、熱狂を生む企業や個人のストーリー、それらの考えに紐づくマーケティング概念などを紹介しています。
「世界で最も必要とされるテクノロジー企業群をつくり、デジタル大国として日本を再生させる」をミッションに掲げる株式会社ギブリー。
2009年の創業以来、時代のニーズに合わせ最速でサービスを提供。近年は最先端のAI技術を活用した革新的なサービスを次々に展開しています。
主軸となるのはHRテック、マーケティングDX、オペレーションDXの3事業。各種プラットフォームやサービスは業種・業態を問わず、多くの企業で導入されています。
そして注目すべきは、「Give&Give」という独自の企業カルチャー。自分が受け取る以上に、常に他人に与え続ける姿勢や精神を、最も大切なDNAと位置付けて挑戦を続けています。
このカルチャーが生み出す社内エンゲージメントと、今後の展望について執行役員の森康真さんと社員の皆さんに伺いました。
目次
坪田さん(以下、坪田):私はエンジニアを含めたデジタル人材の採用や評価・育成などの支援とサービスを提供する、HR Tech部門でマーケティングを担当しています。主な業務としては、オンラインセミナーやオフラインイベントのご案内企画運営、リスティング広告などです。
小澤さん(以下、小澤):オペレーションDX事業部所属です。私の部署は、AIの活用が課題となっている企業様をトータルでサポートする部署です。AI導入のロードマップ策定やチームの育成支援、実際のAI開発支援まで包括的に支援しています。
私自身はパートナーアライアンス業務・コンサルティングのデリバリーが主な担当業務です。前者はビッグテック企業とのやり取りや、教育プログラムの開発支援がメイン。後者は企業のPMO的な立場で研修・ラーニングの企画や、生成AI活用のプロジェクト進行を行っています。
保坂さん(以下、保坂):企業様のマーケティングやセールスのデジタル変革を支援する、マーケティングDX事業部で営業を担当しています。部署としては、MA(マーケティングオートメーション)領域、カスタマーサポート領域に生成AIを掛け合わせてサービスを開発・提供しています。
坪田:高校卒業後に就職した友人たちから「仕事がつらい、早く辞めたい」という話をよく聞いていたんです。よくよく話を聞いてみると、学校や先生の推薦で就職先を決めてしまい、いざ働き始めてからミスマッチに気づくケースが多くて。そうした状況を変えたいと思ったのが、キャリア支援の仕事に興味を持ったきっかけでした。
そんなときに出会ったのがギブリーです。HRテック事業は、仕組みとして質の高い支援を提供しながら、自分もキャリア支援に関われる環境が整っていたんです。ここなら自分のやりたいことが実現できると感じ、入社を決めました。
小澤:私は企業説明会がきっかけで。
説明会などで会話を重ね、「新しい技術に常に挑戦している企業」という印象を抱きました。どんどん新しい技術に触れて、常にチャレンジしているところに惹かれたのが決め手ですね。
保坂:私は情報工学系の学部出身で、大学院に進む人やエンジニアになる人が周りに多かったんです。でも私には、営業スキルやコミュニケーション力を実践で学んでから専門スキルを活かしたいという思いがあってギブリーへ。
入社の決め手となったのは、大きく2つ。
ひとつは多角的にサービスを展開していて、面白そうだと思ったこと。もうひとつは若手でも活躍できそうだと感じたことです。実際、いろんな事業やポジションを経験できているので、「入社してよかった」と思っています。
小澤:就職活動時から感じていたんですが、ギブリーの社員は面接でもとにかく向き合ってくれるんです。入社後も忙しいのを承知で相談したら、それにもかかわらず丁寧にアドバイスをくださる先輩が多くて。「人に向き合う」が当たり前のこととして根付いているなと感じます。
坪田:「まず相手に何を与えられるか」を常に考えているところに「Give&Give」を感じます。営業担当も「このサービスを売らなきゃ」ではなくて、先方がベストな選択をするために必要な情報を提供するんです。だからこそお客様と信頼関係が構築でき、継続的なお付き合いが生まれるんだと思っています。
保坂:マーケティングDXでは、「マーケティング×AI」「チャットボット×AI」というように、技術を組み合わせる場合が多いんです。そこで他部署の皆さんにヒアリングするんですが、それぞれの業務範囲を超えて助けてくれて。サポートし合う文化があるのは、このマインドが根付いているからでしょうね。
保坂:はい、そうですね。
AIリテラシーやプログラミングなどさまざまなコースが用意されていて、社員には使用ライセンスが付与されています。スキルアップできるのはありがたいですし、実際に自社のサービスを使うことでユーザー視点を持ち続けられます。Eラーニングツールで力をつけ、生産性を上げている社員も多いと思います。
小澤:新卒・若手社員にもチャレンジする機会は多くあります。
たとえばインサイドセールスからスタートし、新卒1年目の途中でフィールドセールスに挑戦できるケースもあるんです。また、大手企業のお客様向けのAI関連案件に、若手社員が第一線で関わる機会も多くあります。
20代のうちに、大手企業の部長や役員クラスを相手に大型案件の営業やコンサルティングに挑戦できる場合も。数億円規模のマーケティング予算を動かすなど、経験年数を問わず挑戦のチャンスが豊富です。こうした環境だからこそ、自身のモチベーションも高く保てますね。
坪田:自分が「やりたい」と手を挙げればまかせてもらえますし、それで成果を出せば、さらに大きな案件の担当に。やる気次第でどんどん活躍できる環境だと感じています。
「Givery Times」https://note.com/givery_saiyo
取締役直下で新規事業企画|起業志望だった私が惹かれた「スピード感」と「チャンスの多さ」【内定者インターン紹介 #5】
当社では創業当初から、自分が受け取る以上に、常に他人に与え続ける姿勢や精神を最も大切なDNAとして「Give&Give」と呼んでいます。打算なしで与え続けるからこそ、信頼と人望を得て、価値をお客様や社会へ提供できると考えています。
この考えには、当社の代表である井手の人生観が色濃く反映されています。もともと寿司職人としてキャリアをスタートした彼は、「おもてなし」の概念を身体で覚えたんですよね。お客様の喜びが仕事の大きな原体験になっていて、それが現在にも活かされています。
「最優先にするべきもの」です。
通常、企業では利益を第一に考えると思いますが、私たちが最優先するのは相手への価値提供。たとえば私たちが支援している「JPHACKS(ジャパンハックス)」というイベントもそのひとつです。
これはイノベーターを目指す学生を対象にした国内最大級のハックイベント。全国の理系学生が集まる競争・交流の場で、利益はほぼありません。
しかしそれでも企業として、大変な工数を割いて実施しています。それが将来的には、若手エンジニアの育成や業界の発展につながると考えているからです。
そうですね、赤字覚悟のプロジェクトも「お客様に本当に必要なのであれば」と決行することも多々あります。短期的な利益で考えると正直厳しいですが(苦笑)、継続的なお付き合いの中で、大きなリターンがある場合もあるんです。
俯瞰で物事を見て、量より質を見る。
単純な損得ではなく、役に立ちたい気持ちを持つ。
そうした考え方を企業のDNAとして大切にしています。
チームワークはもちろん、「若手に任せる」という姿勢にもつながっています。当社では成長を重視しているので、マネージャーやリーダーは「やりたい気持ちがあるならぜひ」と裁量を与えます。上司は部下に任せっぱなしではなくて、何か困ったり迷ったりしたら必ず助ける。でも基本はチャレンジしてもらう。
そうすると若手は挑戦しながら成長し、結果として事業の価値も高まっていく、という好循環が生まれるんです。
はい、その通りです。
「利他的な視点で動けるか」「相手に『何をどう与えられるか』を常に考えられるか」といった点は特に重視しています。それによって組織全体が「与える」文化を自然と体現できるようになるので。
人事目線では、若手社員が活躍できる環境をどう整えるか、離職率をどうコントロールするかなどの点でこのカルチャーが効いていると感じますね。
短期的には損だと感じても、人や社会に価値を提供することが、実は会社の競争力の源泉になる。これはギブリーの歩みの中で証明されていると思っています。若手の成長も含め、長期目線で人を育てる。そしてお客様に本当に必要なもの・価値を提供し続けることが、結果として当社にとっても大きな成果につながる。その点で「Give&Give」は、これからの時代に合ったマインドだと信じています。
AIはいまや文章・画像・音声・動画とさまざまな分野で活用されていますが、どこか無機質な印象も。ですがギブリーの皆さんとお話しし、技術の中心にしっかり「人」がいることを感じられました。
部署も立場も違えど、根底に流れる「Give&Give」の精神が自然と人をつなぎ、支え合う文化を育てている。それはまるでAIのコードのように、“共通言語”で見事につながっているよう。
最先端の技術と人間力、その両方に触れられる環境は、まさに今後のビジネスの理想形かもしれません。

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi