資料ダウンロード
rayoutはファンマーケティングを活用した
PRをご支援しています
閉じる

Takanashi
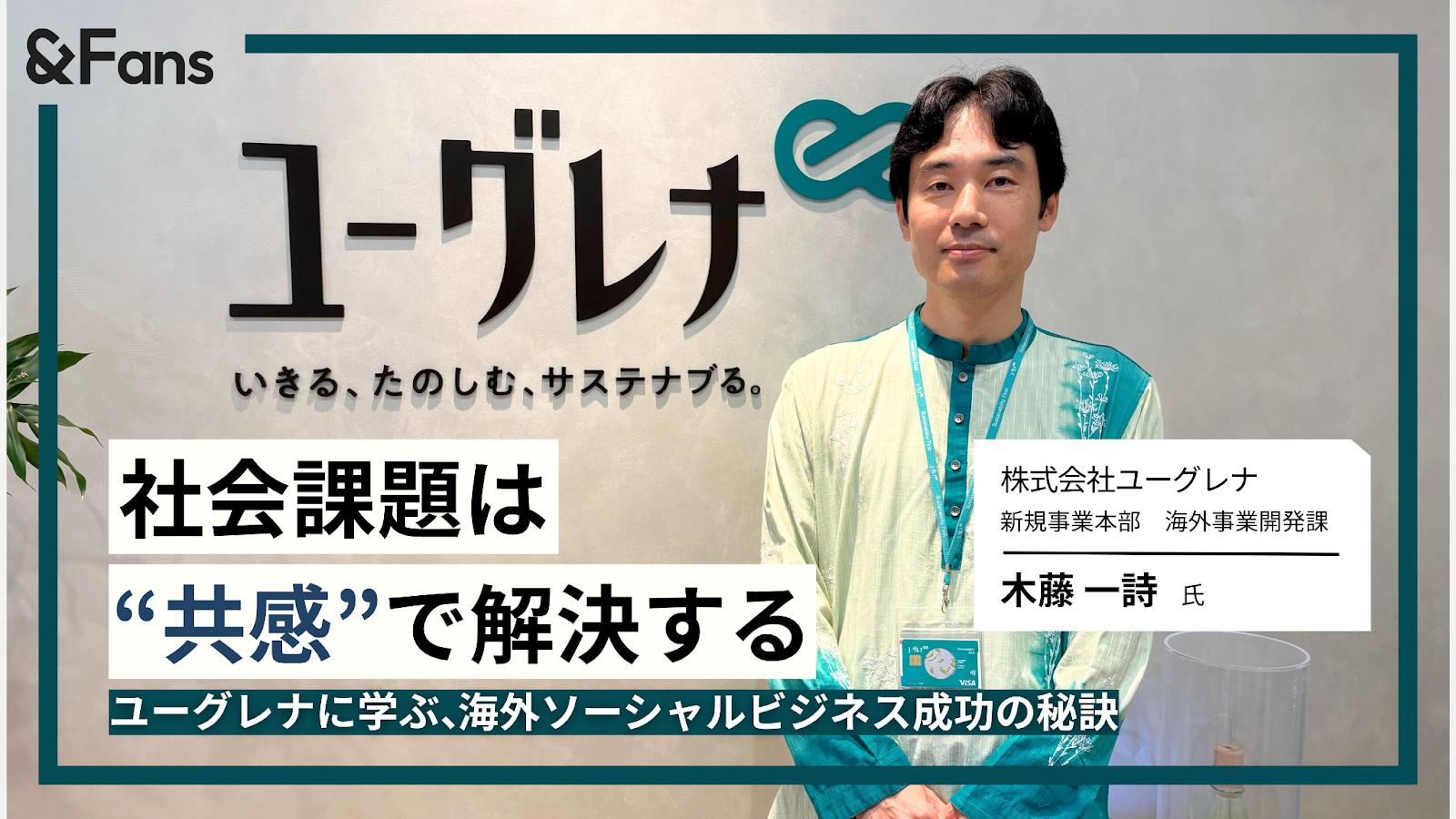

Takanashi
「社会課題の解決」と「経済合理性(利益の追求)」の両立は難しい……。そんな固定観念をお持ちではないですか?
こんにちは、&Fans編集部の小鳥遊です。&Fansでは、熱狂を生むさまざまな企業や個人のストーリー、それらの考えに紐づくマーケティング概念などを紹介しています。
今回は、藻類ユーグレナを活用した製品開発・研究を行う「株式会社ユーグレナ」の海外事業開発課・木藤さんにお話を伺いました。
多くの企業が「経済合理性」を優先するなか、ユーグレナは「社会課題の解決」を起点にした事業展開で、持続可能なビジネスを実現しています。なかでも注目すべきが、バングラデシュでの取り組み。現地の子どもたちに栄養豊富なクッキーを配布したり、農業支援をしたりすることで、バングラデシュが抱える課題解決を目指しています。
今回は、ユーグレナが現地で積み重ねてきた活動を深掘りしながら、異国の地で持続可能なビジネスを築きあげた秘訣に迫ります。
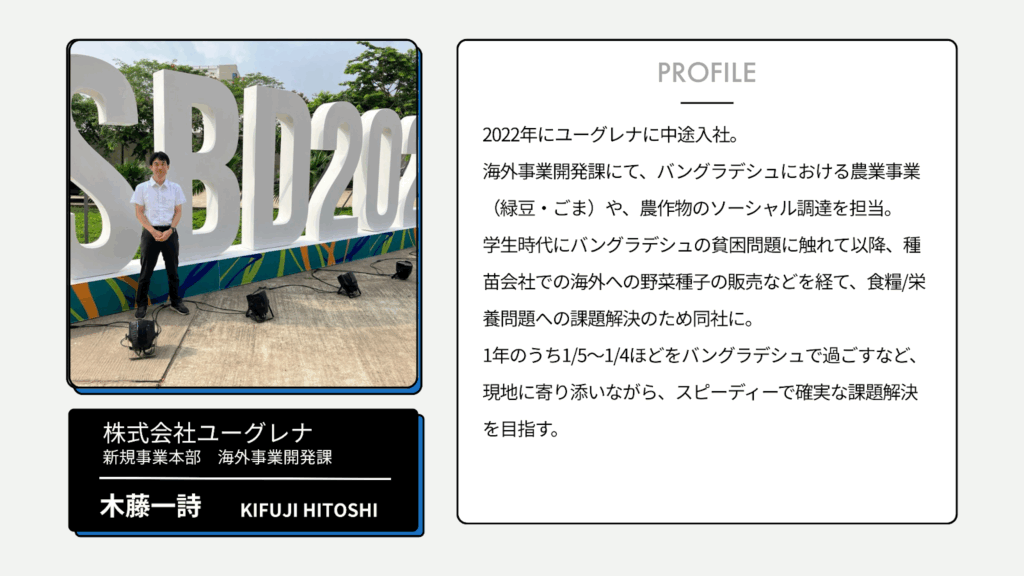
目次
当社は2005年に創業し、今年で20周年という節目を迎えます。創業者の出雲が東京大学在学中に、可能性に満ちた素材「ミドリムシ」と出会ったことを機に立ち上げた会社です。社名には、ミドリムシの学名である「ユーグレナ」を用いており、ある意味「株式会社ミドリムシ」とも言えるかもしれません(笑)。

きっと多くの方がそうですよね。ミドリムシは、植物性と動物性の両方の栄養素を持つ微細藻類です。健康素材として注目され、健康食品の分野で少しずつ認知を広げてきましたが、現在では化粧品やバイオ燃料の開発にも事業を展開しています。さらに、サステナブルアグリテックと呼ばれる農業事業にも力を入れており、3年前から持続可能な循環型農業にも取り組んでいます。
▼化粧品、ヘアケア商品、健康食品の企画・製造・販売を手がけるユーグレナグループ・株式会社エポラについては、こちらの記事もおすすめです。
株式会社エポラ 代表取締役社長 竹村孝介氏「縁を楽しむ」で年商35億-愛媛発「日本一あたたかい通販会社」を目指す竹村社長の経営術-
いえ、日本国内だけでなく、バングラデシュでも事業を展開しています。現地では、グループ会社の「グラミンユーグレナ」のメンバーが農家の方々とネットワークを築き、日本から技術を提供することで、農作物の品質向上に取り組んでいます。その結果、これまで存在しなかった市場へのアクセスを可能にし、現地農家の収益拡大につなげるプログラムを進めています。
創業者の出雲が大学1年生のときにバングラデシュを訪れたことがきっかけです。現地で栄養失調の子どもたちを目の当たりにし「子どもたちに効率よく栄養を届ける方法はないか」と考えたことが、バングラデシュに注目する原点となりました。

さらに、バングラデシュの農家の約9割は1ヘクタール程度の小規模農家で、都市部に比べて貧困率も高いという現状があります。そうした農家の方々の収入を増やす取り組みは、結果的に大きな社会課題の解決につながると考え、私たちはバングラデシュでの事業に力を入れています。
バングラデシュが抱える社会課題は、先ほど申し上げた収入面のほか、教育面や健康面など多岐にわたるため1つに限定できません。ただ、当社は各課題ごとにアプローチするのではなく「ユーグレナGENKIプログラム*」を通じて、包括的な解決を目指しています。

*ユーグレナGENKIプログラム:バングラデシュの子どもたちに、ユーグレナが含まれた栄養豊富なクッキー(画像参照)を届けるプログラムのこと
ユーグレナGENKIプログラムでは、特に貧困地域の学校を中心にクッキーを配布しています。栄養を補えることで健康課題が解決するのはもちろん、子どもたちが「クッキーを食べられるから学校に行こう」と思うことで、就学率も向上します。また、子どもが学校に通っている時間を活用して親が内職に取り組めるため、収入向上も期待できるでしょう。つまり、健康課題にアプローチすることで、副次的に教育や収入などの課題解決にも波及していくのです。
ありがとうございます。クッキーは4種類ほどの味を用意し、子どもたちが飽きずに毎日食べられるよう工夫しています。実は、このユーグレナクッキーを製造しているのは当社ではなく、バングラデシュの老舗メーカーなんです。そのメーカーも社会課題の解決に強い関心を持ち、私たちの取り組みに共感して協力してくださったと聞いています。現地で親しまれている企業とパートナーになれたことは、私たちにとっても大きな意味がありますし、社会課題の解決には“仲間”の存在が欠かせないと強く感じています。
おっしゃるとおりです。ただ、社外に限ったことではなく、社内に対しても同じことが言えます。なかでも、現地で働くバングラデシュ出身メンバーの存在は非常に大きいですね。彼らが私たちと現地の方々をつないでくれることで、言葉の壁がなくなるだけでなく、文化的な理解も深まります。実際に現地のリアルな声を拾い上げたり、調査を行ったりするのは現地出身メンバーなので、よりダイレクトに課題解決するためにも、現地の仲間のサポートは欠かせません。

異国でのビジネスですので「文化の違い」は特に強く意識しています。バングラデシュはイスラム教の国で、ムスリムの方々は1日に5回お祈りをする習慣があるんです。業務時間中であってもお祈りを優先してもらったり、ラマダン期間中は断食を尊重したりと、現地の文化に配慮した対応を心がけています。そうした姿勢が、現地の方々からの共感や信頼につながると考えています。
実は、大きく意識していることはありません。というのも、当社には、既に取り組みに“共感”しているメンバーが集まっているからです。創業者の出雲が社会課題を起点とする“ソーシャルベース”の考え方から「Sustainability First」という理念を掲げており、その理念に共感して入社を決めてくれた仲間が多く集まっています。彼らの存在が、自然とバングラデシュ事業の発展にも大きく貢献してくれていると感じています。
ありがたいことに、多くの企業さまからも共感の声をいただいています。先ほどご紹介したユーグレナGENKIプログラムに関して言うと、お客さまが当社の商品を購入するごとに、約10円がクッキー代金として充てられる仕組みになっています。「商品を10円分、安くしてほしい」という声があがってもおかしくない状況ですが、不満の声を耳にしたことはありません。むしろ「もっと違う方法で参加したい」という声をいただくほどです。
現在は、法人のお客さまから直接寄付を受けられる仕組みを立ち上げたり、ユーグレナのクレジットカードを作ったり、参加の方法を少しずつ増やしています。こうした工夫を通じて、多くのお客さまからご支持いただいていると感じます。

そのとおりだと思います。どちらか一方を叶えるのではなく、両方を実現する必要がある。ただ、当社が取り組む以上、サステナブルであることに意味があると思っています。そのなかで、当社の取り組みに共感してくださる企業さまに向けて、バングラデシュの作物を提案する「ソーシャル調達」の活動も進めています。食品会社さまやソーシャルビジネスの企画・開発に携わる方々に、社会課題の解決につながる原材料を調達していただくことで「社会課題の解決」と「経済合理性」の両立につなげていきたいです。
これまで現地の農家や子どもたちを対象に事業を行ってきましたが、今後は一般の方々にも広げていきたいと考えています。たとえば、ユーグレナの粉末を使った食品や化粧品を現地で販売することで、バングラデシュの市場全体にアプローチしていきたいです。また、国としてバングラデシュの給食事業を始めると伺っています。そのなかで、当社のユーグレナクッキーを取り入れていただけるよう提案していくことも検討しています。
ソーシャルビジネスという難易度の高い事業を行うにあたって、やはり大切なのは、パートナー企業や現地で活動してくれているメンバーなど、仲間の存在だと思います。新たにソーシャルビジネスに取り組まれる企業さまは、特に仲間探しに注力すると、成功に一歩近づくのではないでしょうか。
また、ソーシャルビジネスに取り組む企業同士のネットワークも非常に重要です。先日、バングラデシュで「ソーシャルビジネスデイ」というイベントが開催され、多くの方が集まり情報交換を行いました。そうした場に関心のある方々をつなぐことも可能ですので、「一緒に社会課題を解決していきたい」という方がいらっしゃれば、私たちが仲間になりますので、気軽に声をかけていただけるとうれしいです。

企業が利益を出すことは、事業を続けるために必要不可欠です。
それでも「社会課題の解決」を掲げて取り組むと、「ボランティア活動で十分なのでは?」「課題で利益を得るのは抵抗がある」と感じる人も少なくありません。
しかし、社会課題の解決には長期的な取り組みが必要です。だからこそ、利益を還元し続けられる「企業」が取り組む意義があるのではないでしょうか。ユーグレナを活用した商品の売上を、バングラデシュの課題解決に還元し続ける株式会社ユーグレナは、まさにそれを体現していると言えます。
「正義(ソーシャルビジネス)」と「利益(儲けを出すこと)」は両立できる。いや、両立していかなければいけない。そんなことを確信できた取材でした。
▼「海外の社会課題解決例をもっと学びたい!」そんな方はこちらの記事もおすすめです。
あなたの食事が、世界の子どもの未来をつくる。「TABLE FOR TWO」がつくる、誰もが参加できる社会貢献
取材・執筆:小鳥遊まゆか
編集:神谷周作

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi