資料ダウンロード
rayoutはファンマーケティングを活用した
PRをご支援しています
閉じる
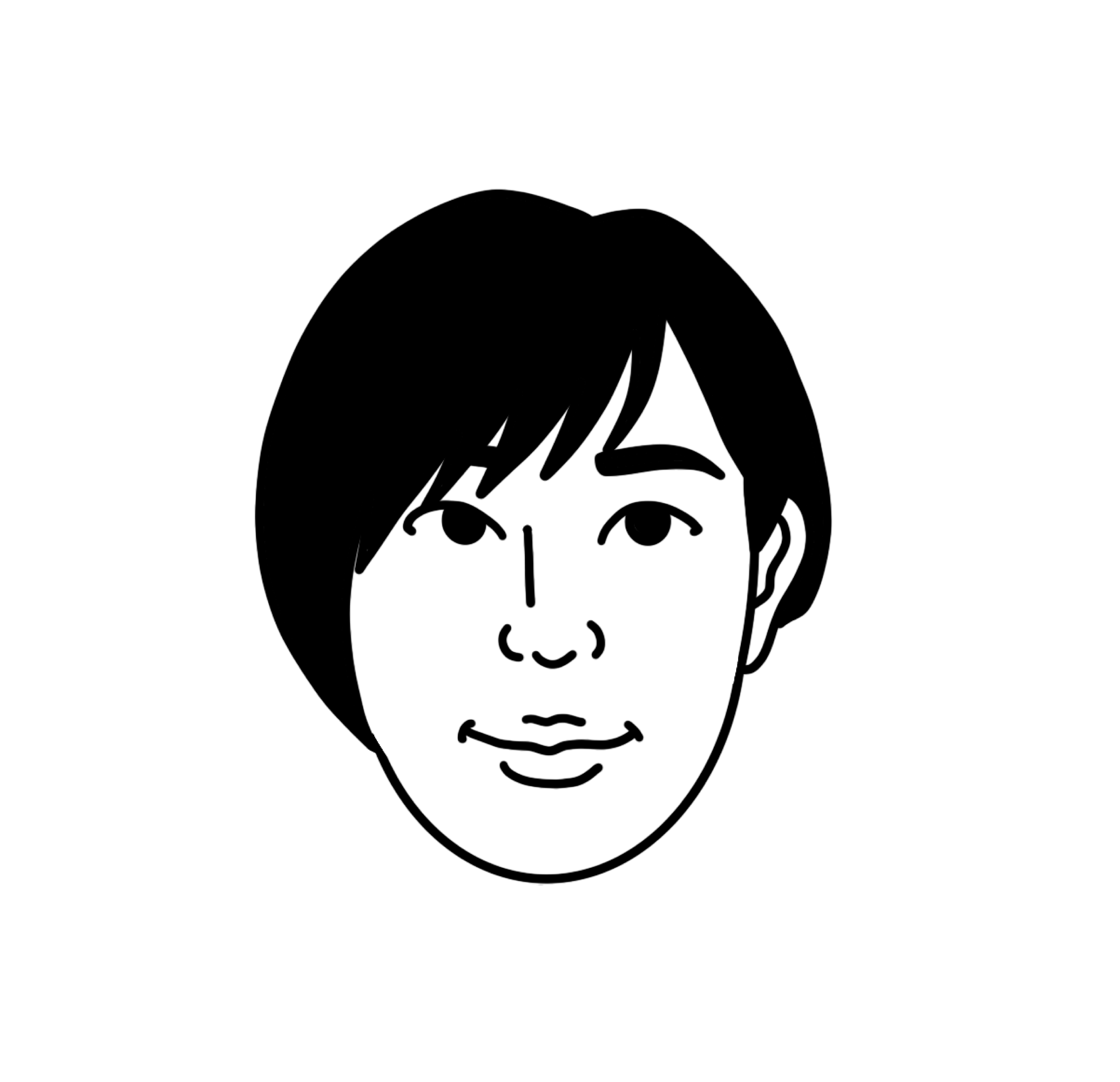
Matsui
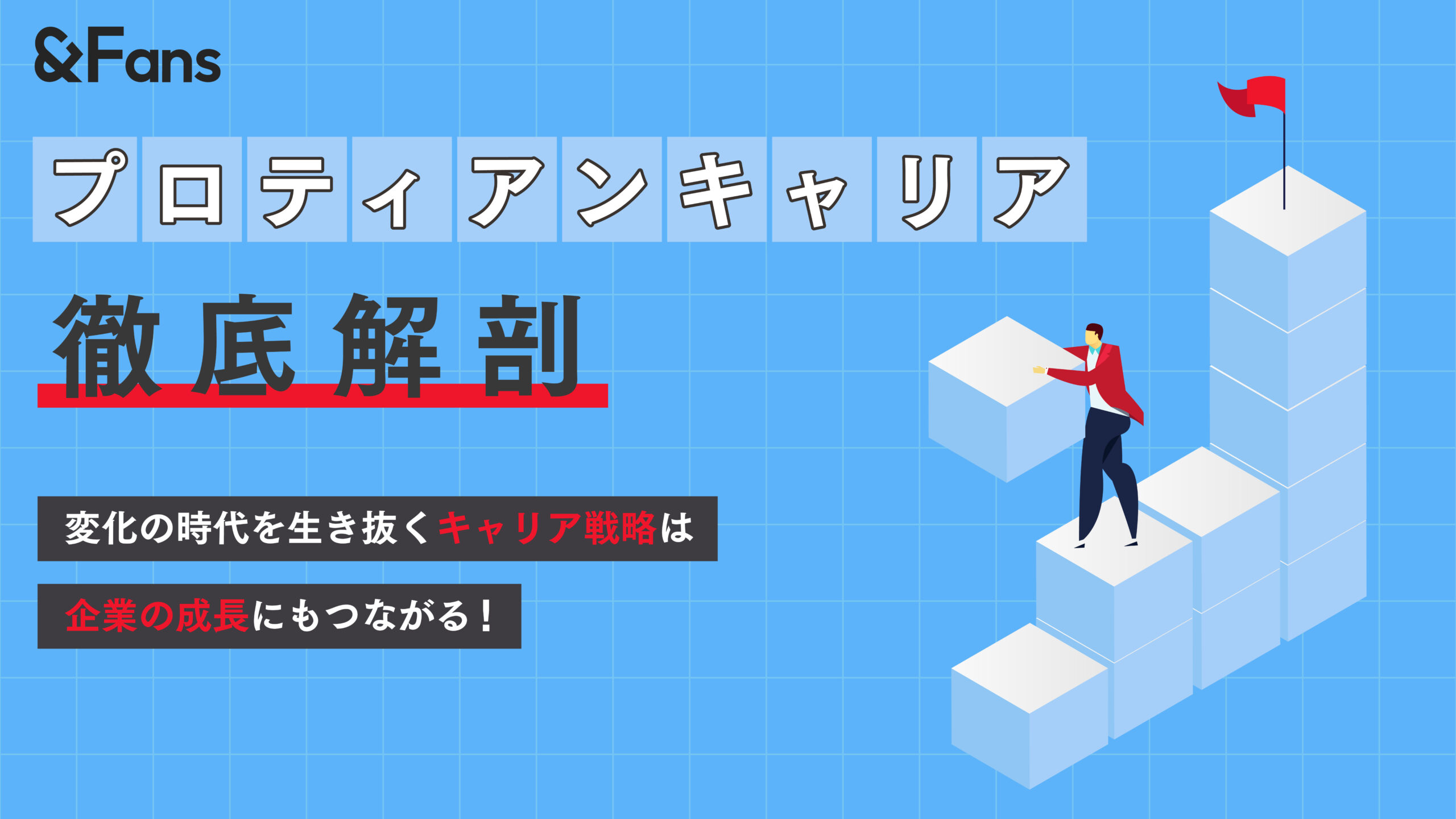
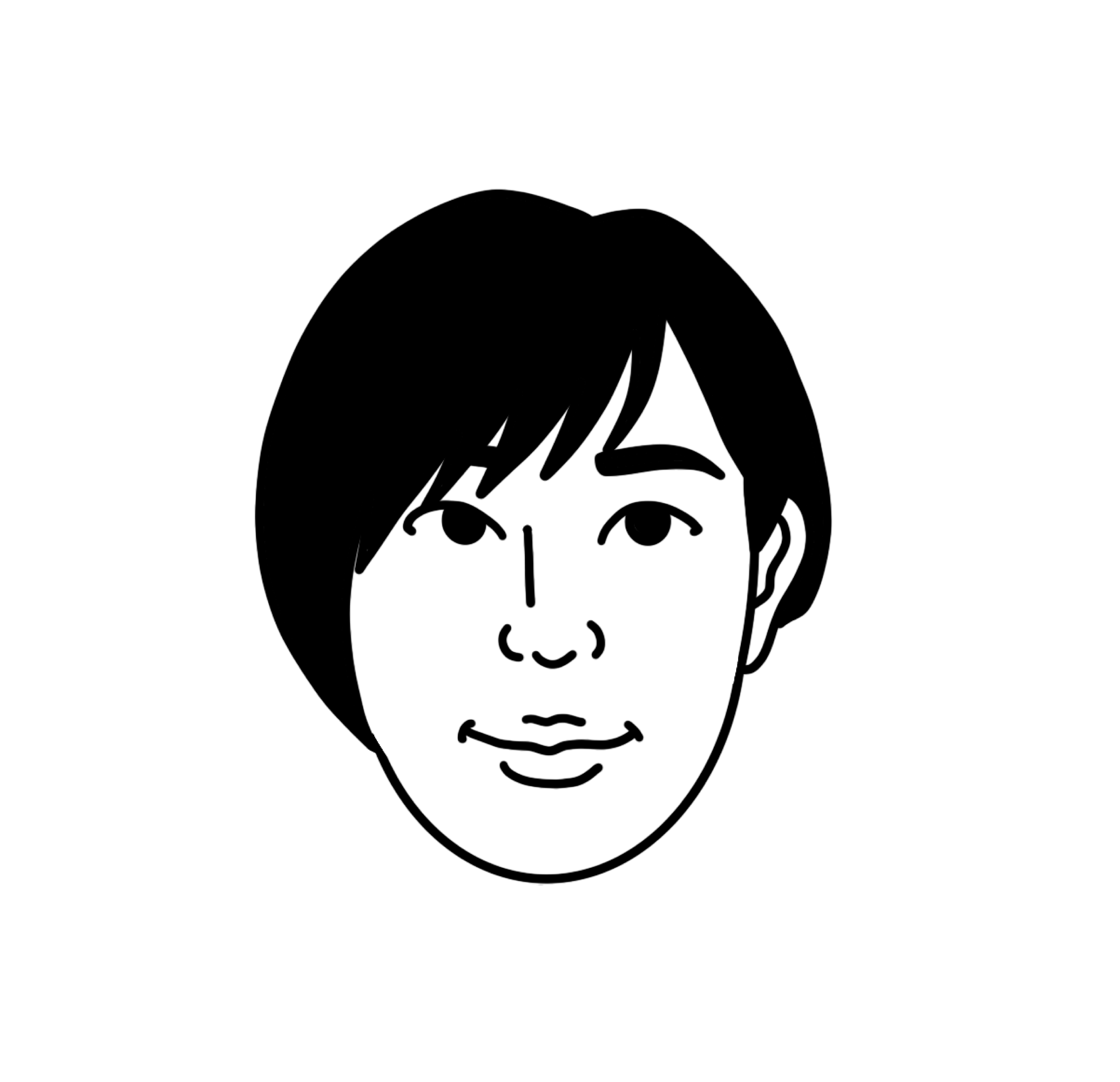
Matsui
こんにちは、&Fans ライターのマツイです。
コロナ禍を契機に、ビジネスや社会は大きく変化しました。特に「働き方」においては、テレワークやオンライン会議が日常となり、キャリア形成の方法も多様化しています。
その中で注目を集めているのが「プロティアンキャリア」です。これは自分の価値観やつよみを軸に主体的にキャリアを築き、変化に柔軟に対応するキャリアの形です。
この記事では10年以上にわたり、人事業務に関わってきた私の経験をもとに詳しく解説していきます。
プロティアンキャリアは企業にも大きなメリットをもたらします。採用担当の方などぜひこちらの記事を参考にしていただければ幸いです!
目次
プロティアンキャリアとは「変化する時代や環境に柔軟に対応し、自らの価値観を基に主体的にキャリアを築く」考え方です。「プロティアン(Protean)」は、「変幻自在な」「変化し続ける」という意味を持ちます。
この概念は、ギリシャ神話の海神プロテウスに由来します。プロテウスは動物や水、大木などさまざまな姿に変身できる能力を持っていたと言われます。
プロティアンキャリアは、1976年にアメリカの心理学者ダグラス・T・ホールによって提唱されました。
アメリカでは1970年代以降、経済停滞や貿易自由化で長期雇用の崩壊と雇用の流動化が進行。不安定な時代を生き抜くため、ホールは「キャリア形成は組織主導ではなく、個人の価値観に基づくべきだ」と主張しました。個人が自分の価値観に従って、変化を受け入れながらキャリアを築くのが重要だと説いたのです。
参考:https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2023/04/pdf/058-061.pdf
現代の社会はデジタル化、グローバル化、AI技術の発展などかつてないスピードで変化を続けています。その影響は企業や仕事、さらには働き手の価値観にも。*VUCA時代に適応するためプロティアンキャリアの考え方が必要となっています。
さらに以前は「転職せず、同じ企業で長く働くべき」との考えが主流でした。しかし今では「転職は当たり前」の価値観が広がり、個人が主体的かつ自由にキャリアを選択する時代に。これもプロティアンキャリアが注目されている理由のひとつでしょう。
*VUCA(ブーカ時代)…物事が不確実で、将来の予測が困難な時代・状況を指す造語。Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字から成る。
従来型キャリアとプロティアンキャリアの大きな違いは、キャリアの主体・目標にあります。
従来型キャリアは企業の力が強く、キャリアにまつわる多くを企業に委ねる姿勢だと言えるでしょう。対するプロティアンキャリアは、主体性を持ちながら状況に応じて自分自身を変化させていく柔軟なキャリア形成の姿だと言えます。
プロティアンキャリアを語るうえで欠かせないのは、メタコンピテンシー(学習能力)。メタコンピテンシーはアイデンティティとアダプタビリティ、この2つの能力から構成されます。
アイデンティティとは「自分は何者なのか」を自覚すること。プロティアンキャリアでは、自分の価値観や目標、興味・関心に基づいてキャリアをデザインします。他者の期待ではなく、自分自身の望む姿を追求すると言えるでしょう。
従来型キャリアでは「組織の役割」「周囲からの見え方・尊敬」が軸となり、拠り所は自分ではなく他者にありました。評価基準を他者に求めて自己が確立できないと、周囲や環境の変化に振り回されてしまい疲弊しかねません。
アダプタビリティは時代や環境の変化に柔軟に対応するスキルを指します。新しい技術や市場の変化にも素早く対応できる力とも言えるでしょう。キャリアの分野では「キャリア・アダプタビリティ」と呼ばれる場合もあります。
アダプタビリティは「適応コンピテンス」と「適応モチベーション」の2つから成り立ち、一方が欠けると成立しません。適応コンピテンスは以下の3つの要素から成り立っています。
適応モチベーションは適応コンピテンスを成長させたり、状況にあわせて適応コンピテンシーを活用する意思を指します。アダプタビリティは当然ながら一朝一夕に身につくスキルではありません。
常に自分の望む姿を考えつつ、自身の姿・考えを変容していくPDCAともいえるサイクルが重要です。
プロティアンキャリアの考え方を示してきましたが、なかには優秀な人材の流出を危惧する人もいるかもしれません。もちろん本人の目指す姿が現在の業種・職種と大きく離れていれば、離職につながる可能性はあります。
ただプロティアンキャリアはあくまでも離職を促す考え方ではなく、現在勤務する企業でも十分に活用できる考え方なのです。従業員が主体的に考え、行動すると企業にも以下のようなメリットが生まれます。そのため企業としても、プロティアンキャリアについて従業員が考える機会を設けるのは重要と言えます。
プロティアンキャリアを意識する従業員は、急速な市場変化や新しい技術に迅速に適応できます。時流を的確につかみ対応策を導き出す力は企業の大きな財産であり、重要な人材でもあると言えます。
自己成長を目指す従業員が増えると業務効率が上がり、生産性も向上します。自律的にスキルを磨く従業員が多い環境は、企業全体のパフォーマンス向上にもつながるでしょう。
プロティアンキャリアの支援は従業員の満足度を向上させます。自分のキャリアを自らの意思で選べる安心感は、従業員にとって心強いもの。結果としてエンゲージメントの向上や離職率の低下につながります。
多様な経験を積んだ従業員は異なる視点からアプローチしたり、アイデアを生み出しやすくなります。これらはすべてイノベーションの種であり、企業の成長を後押しします。
プロティアンキャリアを支援する企業は、柔軟で成長志向のある職場として認知されます。ポジティブなイメージは他社との差別化につながり、採用活動を有利に進めるための強力な武器になります。
プロティアンキャリアは個人が主体性を持つ考え方ですが、その考えを支援する企業も増えてきています。副業の解禁やリスキリング支援はそのひとつでしょう。
ビジョンが見えない、つよみが見つからないと嘆く従業員には気付きを与え、モチベーションを高める効果も期待できます。
従業員の「学びたい」に応え、新しい知識を学ぶ機会や場を提供するのは非常にいい手段です。
これらは一例ですが、新たな学びや出会いはアイデンティティのアップデートにもつながります。さらにスキル=実務に直結する能力だけととらえずに、マインドセットやタイムマネジメントなど広くとらえるべきでしょう。
たとえば職種に関係なく、財務・会計の研修を受講させてもいいのです。試算表に基づく数値の正確な分析・把握が可能となれば成果の向上や課題の把握がどの職種においても期待できます。
メンターや上司との1on1ミーティングなどを実施し、個々の目標やスキルを確認します。ここで重要なのは個人の考えや意見を否定しないことです。
「現実的でない」「憧れているだけでしょう?」「前例がない」……これらは本人が一番よく分かっていて、課題だと感じている部分です。アドバイスやフィードバックは有益ですが、否定は何も生み出しません。
「それならどう行動する?」「どんなプランを描いている?」と話しているうちに本人の考えが整理される場合も多々あります。さらにこの取り組みは従業員のキャリア形成をサポートするだけでなく、組織の方向性と個人の成長を一致させる効果もあります。
異なる部署や業務を経験するジョブローテーションの整備は、従業員の多様なスキル習得を促進します。新しい業務にチャレンジする大変さはありますが、「できない」と決めつけていた思い込みを払拭するチャンスかもしれません。
ジョブローテーションは個人の隠されていた力を引き出し、新たなキャリアを考えさせるきっかけにもなります。従業員の意志を尊重した機会を提供できる、これは企業にも従業員にも重要なポイントです。
企業ではさまざまな人が働いています。育児・介護をしながら働く人もいれば、病気と付き合いながら働く人も。その中でキャリア支援が「バリバリ仕事に打ち込める人」だけのものになってしまってはいけません。
フレックスタイム制や時短勤務制度、リモートワークの導入など幅広い働き方の提供もキャリア支援につながります。自分のペースで仕事に取り組める環境は、自律性を促し次のステップへポジティブに導くでしょう。
★自己管理型組織が気になる人にはこちらもおすすめ★
次世代の組織のあり方:ティール組織とは?自己管理型の未来組織がもたらすビジネス変革
プロティアンキャリアは、変化の激しい現代社会で自分らしいキャリアを築き、長く働き続けるための有効なキャリアです。自己の価値観を大切にしながらスキルを継続的に磨けば、変化に柔軟に対応できます。
一方でプロティアンキャリアには、変化するからこその不安定さやリスクも伴います。しかし適切に自己を見つめ、ときには考え方を変えながら進んでいけば大きな満足感を得られるでしょう。
より深く知りたい方には、一般社団法人プロティアン・キャリア協会が実施する講座や検定がおすすめです。
自分らしく働き、キャリアを築いていくことは企業にとってもプラスになります。新しいアイデアは風を吹き込み、他者に刺激を与え、ポジティブな循環が動き出します。個々の力が強くなれば、組織としてもパワーアップするに違いありません。
従業員は自分の内なる声を無視せず、ビジョンをしっかりと描き、企業はキャリアパスを押し付けず、従業員に無理なく併走する。そのような関係性を築けたら、組織はお互いによりよい形で成長できる場になるのではないでしょうか。
プロティアンキャリアの考え方が、従業員・企業双方にメリットをもたらすものとなるよう心から応援しています!
自分がプロティアン人材かを診断する「プロティアンキャリア診断」を掲載します。当てはまる項目がいくつあったかチェックしてみましょう。
チェックの合計数で、現在の状態が分かります。
| チェックの数が12個以上=プロティアン人材! |
| 普段から自分のキャリアを考え主体的に形成し、環境や社会の変化に対応できるスキルを持っています。 |
| チェックの数が4~11個=セミプロティアン人材 |
| キャリア形成はできているものの、変化への対応力は弱め。もう一歩踏み出すことでプロティアン人材になれる可能性を秘めています。 |
| チェックの数が3個以下=ノンプロティアン人材 |
| 現状のキャリア維持にとどまっている状態。変化をポジティブに考え、新しい世界をのぞいてみましょう! |
上記はあくまで「現在」の状態を示しています。これからの行動でチェックの数は増やしていけます。プロティアン人材を目指す人は、チェックがつかなかった箇所を意識してみてください。
また診断項目は資本によって分類されます。自分のストロングポイント・ウィークポイントを把握するのに役立ちますね。
みなさんの結果はいかがでしたか?
筆者は社会関係資本は充実しているのに、ビジネス資本はイマイチとアンバランスな状態が浮き彫りになりました。
ただ、ここからどう行動するかは自分次第。個人的にはストロングポイントを伸ばすもよし、ウィークポイントを克服するのもよしだと思います。迷ったときには「何をすれば一番なりたい姿に近づけるか」と考えてみてもいいでしょう。
★社会関係資本が気になる人にはこちらもおすすめ★
アルムナイネットワークとは?退職者と繋がるコミュニティの重要性を解説!
……
&Fans を運営する rayout 株式会社ではrayout では採用から組織運営・整備のお手伝いをしています。何からはじめたらいいかわからない、方針を決めるにあたってアドバイスがほしい…など、さまざまなお悩みを解消いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi